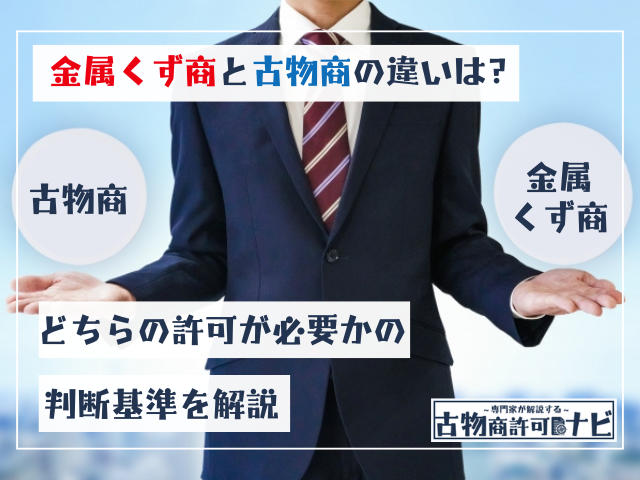

金属くず商と古物商って似てるけど何が違うの?
どちらの許可を取得すればいいのかわからない…

という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、金属くず商と古物商の違いについてや、どちらの許可が必要なのかをどのように判断すればいいかについて分かりやすく解説します。
この記事を書いた人
金属くず商と古物商の違い

金属くず商と古物商では以下の3つの点が大きく異なります。
取扱うモノの違い
| 金属くず商 | 古物商 | |
|---|---|---|
| 取扱うモノ | 鉄、アルミ、スチール、銅、など | 美術品、衣類、時計、宝飾品、車、バイク、自転車、カメラ類、事務機器類、カバン、書籍、金券など |
古物商許可とは,、「中古品」を売買や交換して「営業(商売)」するための許可のことです。
ここでいう「中古品」には、使用済み品や未使用でも使用目的で取引された物(新古品など)も該当します。
一方で、金属くず商とは、「金属くず」を売買して営業(商売)をするための許可のことです。
ここでいう「金属くず」とは、中古品として再使用されるものではなく、本来の目的では使われずに、金属の原料として売買・加工されるものを指します。
たとえば、使わなくなった金属製品をスクラップとして売るような場合が該当します。
根拠法令の違い
| 金属くず商 | 古物商 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 都道府県の条例 | 法律(古物営業法) |
金属くず商と古物商では、制度が設けられた根拠となる法令が異なります。
金属くず商は、都道府県の条例により定められているため、都道府県によって許可が必要だったり、不要だったり対応が異なります。
一方で、古物商は古物営業法という法律によって定められているので、中古品の売買をするのであれば、どこの都道府県でも古物商の許可が必要となります。
営業範囲の違い
| 金属くず商 | 古物商 | |
|---|---|---|
| 営業範囲 | 都道府県内 | 全国 |
金属くず商は、都道府県ごとの条例で定められているため、営業できるのは原則として許可を受けた都道府県内のみです。
別の県で営業したい場合は、その県であらためて許可を取得する必要があります。
また、金属くず商許可で認められるのは、営業所に持ち込まれた金属くずの買取です。
たとえば、解体現場などに出向いて買い取る場合は、別途「金属くず行商届出」が必要になります。
一方で、古物商は全国共通の法律で定められており、たとえば東京都で許可を取得すれば、他県でも届出なしに中古品の買取を行う事ができます。
ただ、古物商に関しても別の件で営業所や店舗を設ける場合には、警察署に営業所追加の届出を提出する必要があります。
金属くず商と古物商のどちらを取得するかの判断基準

金属くず商と古物商は、取扱う製品によってはどちらの許可が必要なのか判断が迷うケース多いです。
この場合、「その製品をどのような用途で販売するのか」で判断するとわかりやすいです。
たとえば、金属製のストーブをそのままストーブとして販売し、購入者もストーブとして使うなら古物商の許可が必要です。
一方、金属製のストーブを金属の原料として販売する場合は、金属くず商の許可が必要になります。
なお、たとえ金属製であっても、中古品として売買するのであれば金属くず商の許可は不要です。
逆に、鉄製の中古品であっても、金属くずとして売買するなら古物商の許可は不要となります。
誤った許可で営業した場合には罰則のリスクがある
誤った許可で営業してしまった場合には、無許可営業とみなされ、罰則の対象となる可能性があります。
たとえば、本来は古物商許可が必要な取引を金属くず商の許可だけで行っていた場合には、古物営業法違反となります。
古物営業を無許可で行った場合には、『3年以下の拘禁刑』又は『100万円以下の罰金』もしくはその両方が科されてしまう可能性があります。
一方で、金属くず商の許可が必要なのにも関わらず、古物商許可だけで営業してしまった場合には、各都道府県の条例違反となります。
金属くず業を無許可営業で行った場合には、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処される可能性があります。
そのため、自分の取引内容に合った許可を正しく判断して取得するようにしましょう。
また、どちらの許可を取得すればいいか分からない場合に専門家に相談してみるのも選択肢の一つです。
NAGASHIMA行政書士事務所では、どちらの許可が必要なのかの的確な判断はもちろんのこと、それぞれの許可の取得や、取得後の運用に関する相談までサポート致します。
\まずはお気軽にご相談下さい/
▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。
古物商と金属くず商の両方を取ればできること
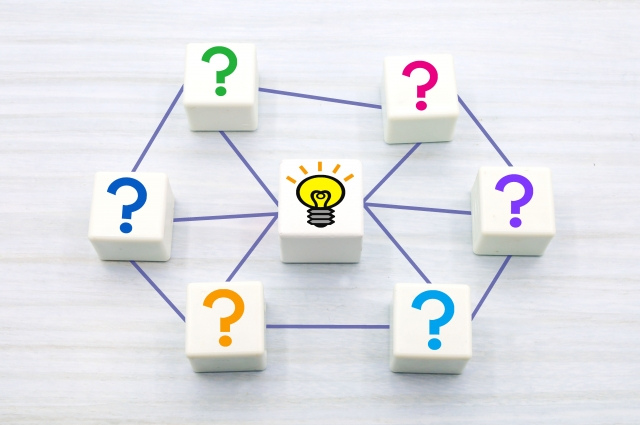
基本的に、古物商の許可が必要なケースでは金属くず商の許可は不要であり、金属くず商の許可が必要なケースでは古物商の許可は不要です。
そのため、通常は自社のビジネスに合ったどちらか一方の許可を取得すれば問題ありません。
しかし、両方の許可を持っていることで、扱える取引の幅が広がります。
たとえば、金属くずとして買い取ったものの中に、状態がよくてそのまま使える製品が混じっていることもあります。
金属くず商の許可しか持っていない場合は、それらも「金属くず」として処分するしかありません。
一方で古物商の許可もあれば、そうした製品は中古品として販売することができます。
中古品としての価値があるものを、わざわざ鉄くずにせずに販売できるのは大きなメリットです。
逆に、古物商の許可だけでは、明らかに製品としては使えないような金属片などを買い取ることはできません。
このような場合でも、金属くず商の許可があれば、スクラップとして買い取り・販売することが可能になります。
つまり、両方の許可を持っておくことで、現場での判断に柔軟に対応でき、ビジネスチャンスを逃しにくくなるというわけです。
産業廃棄物収集運搬業許可との相性もいい
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動によって排出された廃棄物(いわゆるゴミ)を運ぶことができる許可で、金属くず商の許可と非常に相性が良いとされています。
たとえば、ある事業現場から金属くずの買取依頼を受けたとします。
しかし現地に行ってみると、買取できる鉄くずはほとんどなかった――というケースも十分にありえます。
このとき、金属くず商の許可しか持っていない場合は、何も買い取れずにそのまま引き返すしかありません。
一方で、産業廃棄物収集運搬業の許可も持っていれば、たとえ買い取れるものがなかったとしても、廃棄物の回収・運搬を行い、その費用を請求することができます。
また、金属くずの多くは家庭からではなく事業所から排出されることが多いため、産業廃棄物の収集のついでに、鉄くずを買取って販売できれば、より大きな利益につながる場合もあります。
しかし、その際に産業廃棄物収集運搬業の許可しか持っていないと、金属くずはあくまで廃棄物として処理施設へ運ぶことしかできません。
つまり、どちらの許可も持っていることで、現場の状況に応じて「買取」も「回収」も選択できるようになるというわけです。
NAGASHIMA行政書士事務所では、金属くず商はもちろん、古物商や産業廃棄物収集運搬業許可の申請もサポート可能です。
「どの許可を取得すればいいか分からない…」といったご相談でも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
\まずはお気軽にご相談下さい/
▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。
まとめ
この記事のまとめ
- 金属くず商と古物商は取扱うモノに違いがある
- 金属くず商と古物商は根拠法令に違いがある
- 金属くず商と古物商は営業できる地域に違いがある
- どちらが必要かはどのような用途で販売するかで判断できる

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所