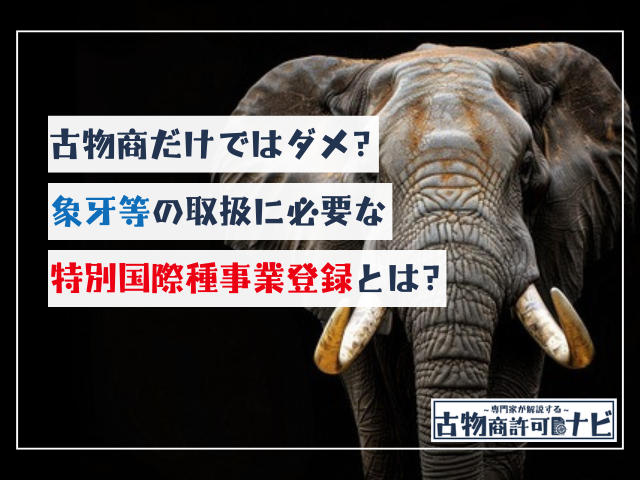

象牙などが使われた製品も古物商があれば取扱い可能?
特別国際種事業登録って何?

このような疑問はありませんか?
象牙などが使われている商品を取扱う場合、例え、それが中古品であっても古物商を持っているだけでは取扱う事はできず、特別国際種事業登録が必要です。
ただ、特別国際種事業は専門的な知識が必要で、細かなルールや、守らなければいけない義務も多く、象牙等を取扱うのが不安という方も多いです。
そんな方は、弊所にお気軽にご相談下さい。
弊所では、古物商はもちろん、特別国際種事業の登録の代行や、象牙取扱い時の法律的な相談対応も行っております。
\まずはお気軽にご相談下さい/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\5秒で気軽に相談/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
また、この記事では象牙等の製品を取扱う場合に、古物商だけではダメな理由や、特別国際種事業登録とは、特別国際種事業登録の義務や取得の流れについて解説しています。
象牙等の取り扱いを検討している方は、是非、最後まで読んでください。
特別国際種事業登録とは?

特別国際種事業登録とは、象牙など絶滅のおそれがある野生動植物由来の製品を、販売や買取などの事業として取り扱う場合に必要となる国の登録制度です。
これは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づくもので、環境省の認可を受けた登録機関に申請し、審査を経て登録されることで、適正な取引が可能になります。
この制度の背景には、ワシントン条約(CITES)により国際取引が規制されている動植物の国内流通を、適切に管理するという目的があります。
中でも象牙は、密猟や違法取引のリスクが特に高いため、この登録制度によって流通の正当性を明確にし、違法な取引を防止する仕組みが整えられています。
したがって、登録を受けていない事業者が象牙製品を事業として売買・貸出・譲渡することはできません。
古物商だけではNG?特別国際種事業登録との違いとは?

古物商許可を取得していれば、中古品全般の売買は可能です。
しかし、象牙やその加工品の中古品を取引するには、古物商の許可だけではできません。
なぜなら、古物商許可はあくまで中古品一般を扱うための許可に過ぎず、象牙のような特別な規制対象品を取り扱うには、特別国際種事業登録が別途必要だからです。
そのため、象牙などを使用した以下のような商品を取扱う場合には「古物商許可+特別国際種事業登録」が必要となります。
| 古物の分類 | 具体例 |
|---|---|
| 美術品類 | 彫刻作品、置物、根付、細密彫刻など |
| 時計・宝飾品類 | ブレスレット、ネックレス、帯留め、かんざしなど |
| 道具類 | 印鑑、ピアノ鍵盤、バイオリンの弓、尺八、将棋の駒、麻雀牌、囲碁の碁石、パイプやシガレットホルダー、万年筆など |
特別国際種事業に関する罰則
特別国際種事業者としての登録を行わずに、象牙製品などの取引を事業として行ったり、義務を怠った場合には種の保存法により厳しい罰則を科される可能性があります。
具体的には、以下のような罰則を科される可能性があります。
実際、過去には12人の古物商らが書類送検されている事例もあります。(WWFジャパン|国内での象牙取引で違法事例再び 古物商ら12人が書類送検されるも不起訴に)
そのため、象牙製品などの取引を事業として行う場合には、必ず特別国際種事業者登録を行い、法律を守って正しく取引するようにしましょう。
特別国際種事業登録に必要な書類と流れ

特別国際種事業登録を行うには、単に申請書を提出するだけでなく、複数の書類を整え、段階的な手続を踏んでいく必要があります。
申請にあたっては、まず「申請者が登録対象として適格であるかどうか(欠格事由の有無など)」を確認し、そのうえで必要書類の準備を進めます。
法人か個人か、また保有している象牙の形態(加工品か全形牙か)によっても、必要となる書類が一部異なる点に注意が必要です。
以下では、登録の具体的な流れ、必要書類、費用の詳細について個別に解説していきますので、申請の準備を進める際にぜひ参考にしてください。
特別国際種事業登録の流れ
特別国際種事業登録は以下のような手順で進めます。
特別国際種事業登録の必要書類一覧
特別国際種事業登録の申請に必要となる書類は以下となります。
| 必要書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 申請書 | 〇 | 〇 |
| 誓約書(法人・個人用) | 〇 | 〇 |
| 誓約書(役員用) | 〇 | × |
| 履歴事項全部証明書 | 〇 | × |
| 身分証明書コピー | × | 〇 |
ちなみに、既に象牙製品等はある場合や、全形象牙がある場合には必要書類が異なる点は注意が必要です。
特別国際種事業登録に掛かる費用
特別国際種事業の登録に掛かる費用は以下となります。
| 費用 | |
|---|---|
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 登録手数料 | 33,500円 |
| 合計 | 123,500円 |
因みに、上記の費用はあくまでも登録審査の通過後に支払うため、古物商の許可のように不許可の場合には手数料が返金されないということはありません。
特別国際種事業登録の有効期限と更新

特別国際種事業者の登録には有効期限があり、その期間は5年間と定められています。
この5年を過ぎても引き続き事業を継続したい場合は、有効期限が切れる前の1年半(=18か月)以内に「更新申請」を行う必要があります。
そして、更新申請を行わずに期限を過ぎてしまうと、登録は自動的に失効します。
しかも、その理由にかかわらず、一度失効した登録を「更新」として扱うことはできず、復活させることもできません。
もし失効後に再び事業を行いたい場合は、新規申請としての手続きが必要となり、登録免許税90,000円と登録手数料33,500円、合計123,500円が改めてかかってしまいます。
そのため、事業を継続する予定のある方は、有効期限をしっかり確認のうえ、忘れずに更新申請を行うようにしましょう。
因みに、更新時にかかる費用は手数料32,500円です。
特別国際種事業の登録後の義務

特別国際種事業者として登録されたあとも、事業者にはさまざまな義務が課されます。
具体的には以下の5つの義務を守る必要がある点には注意が必要です。
取引記録の記載・5年間保存
象牙製品などを適正に取引するためには、古物商と同じように、販売・仕入れなどの内容を「記載台帳(様式第5)」に、きちんと記録し5年間保存することが法律で義務づけられています。(種の保存法第33条の11)
この記録は、必要に応じて環境省や経済産業省に提出を求められることもあるため、正確に抜け漏れのないように記載を徹底する必要があります。
また、記載に使う様式は原則として省庁が指定する様式を使用する必要がありますが、法定の記載内容を満たしていれば、自社にとって管理しやすいフォーマットを使うことも可能です。
変更・廃止の届出(30日以内)
特別国際種事業者として登録した内容に変更があった場合や、事業を廃止する場合には30日以内に届出を提出する必要があります。(種の保存法第33条の7、種の保存法第33条の9)
具体的には、以下のような内容に変更があった際には、自然環境研究センターに変更届を提出しなければなりません。
ちなみに、特別国際種事業の登録も古物商と同様に、法人成りや個人成り、誰かに事業を引き継ぐことはできないので、廃止と新規登録手続きが必要となります。
登録番号等の表示義務
特別国際種事業者は象牙製品などを「陳列」または「広告」する際には、特定の情報を消費者にわかるように表示しなければなりません。(種の保存法第33条の11)
この表示義務は、有償・無償や販売場所(店舗、露店、インターネットなど)には関係なく、全ての場合に表示する必要があります。
例えば、非売品の展示や個人のSNS投稿であっても、対象となる製品を取り扱っている場合は、所定の情報を公衆が確認できるよう掲示しなければなりません。
ちなみに、表示しなければならない内容は以下となります。
- 登録番号
- 事業者の氏名(または法人名)
- 事業者の住所
- 法人の場合は代表者の氏名
- 対象となる特別特定器官等の種別(例:「ぞう科の牙およびその加工品」)
- 登録の有効期間の満了日
表示の書式や大きさには決まりはありませんが、見やすくなければなりません。
管理票の作成と写しの保存
特別国際種事業者が象牙製品等を新たに取得した場合、その製品が重量1kg以上で長さが20cm以上の場合には、「管理票」というものを作成しなければなりません。(種の保存法第33条の23)
この管理票とは、環境省・経済産業省が定めた様式第6に基づき、製品の詳細な情報を正確に記載して管理するためのものです。
そして、管理票は、対象製品を譲渡・引渡しする際に相手方へ渡し、譲渡・引渡しした日から起算して5年間は写しを保存する必要があります。
ちなみに、1kg以上・20cm以上に該当しない象牙製品等であっても、管理票を任意で作成することは可能です。
ただし、任意であっても管理票を作成した場合には、同様に写しを相手に渡し、その写しを保存する義務が発生してしまう点は注意が必要です。
報告徴収や立入検査への対応
特別国際種事業者には、登録後も適切な事業を運営する必要があり、その一環として環境省や経済産業省による「報告徴収」や「立入検査」への対応が義務付けられています。
報告徴収とは、当局から求められた際に、所定の記載台帳を提出する手続きのことです。
これは定期的に実施されることもあれば、必要に応じて突発的に行われることもあります。
また、立入検査は、事業所に直接担当者が訪問し、現場の状況や記録書類などを確認するもので、事業者として調査を受け入れ、質問にも誠実に応じなければなりません。
万が一、報告を拒否したり、立入検査を妨げたりすると、種の保存法に基づく罰則の対象となるおそれがあるので注意してください。
特別国際種事業者の登録は行政書士に依頼可能

ここまで特別国際種事業について分かりやすく解説してきましたが、中には、、、

自分で登録手続きをできるか不安…
法律を適切に守って営業できるか心配…

という方もいるかと思います。
そのような場合には、行政書士に特別国際種事業者の登録を依頼することも可能です。
行政書士に依頼することで、スムーズに特別国際種事業者の登録手続きを進められるだけではなく、登録後も手続きの疑問や不安の相談も可能です。
NAGASHIMA行政書士事務所でも、古物商の許可だけではなく、特別国際種事業者の登録も取り扱っておりますので、ぜひ、お気軽にご相談下さい。
| 費用 | |
|---|---|
| 特別国際種事業者の登録の代行費用 | 44,000円 |
\まずはお気軽にご相談下さい/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\5秒で気軽に相談/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
古物商許可を取得するなら古物商許可ナビ代行
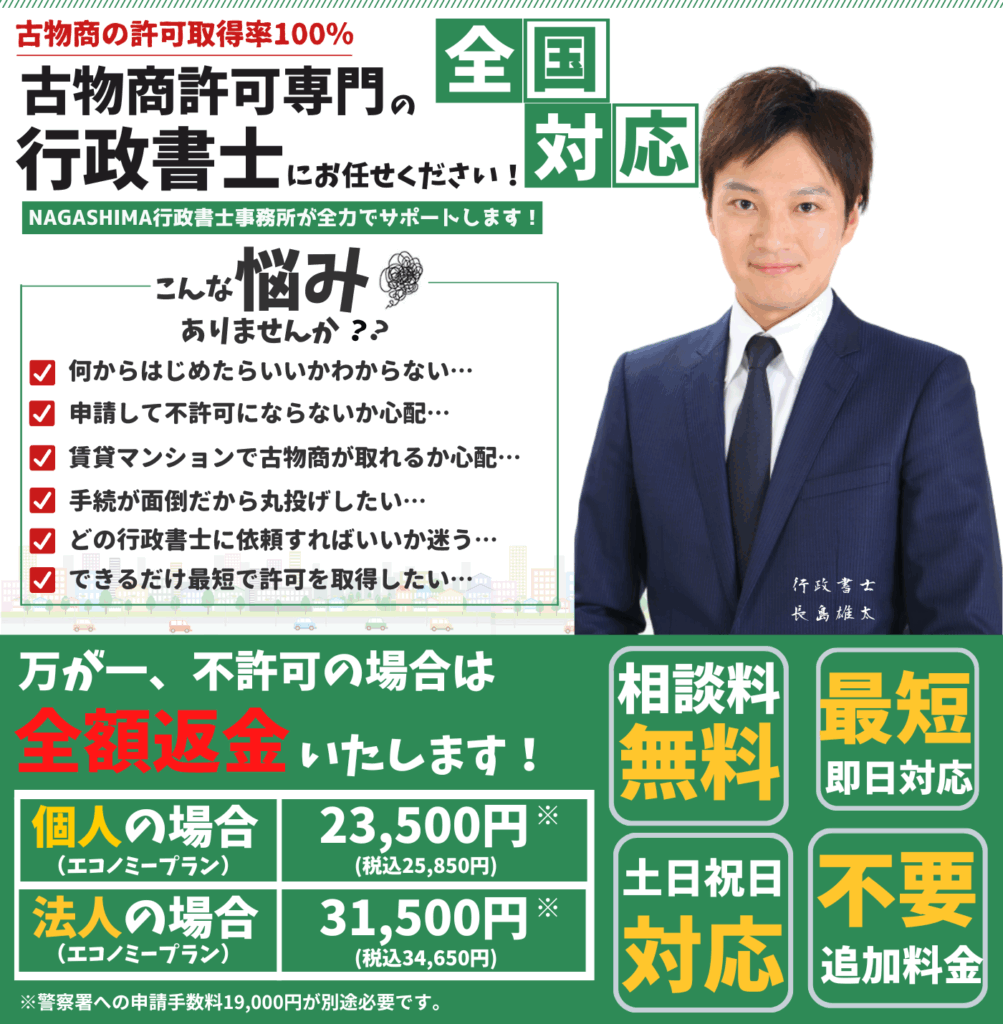
\最短3日で申請可能/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\5秒で気軽に相談/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- 象牙などの製品は古物商だけではできない
- 象牙などの製品を取扱う場合には特別国際種事業者の登録が必要
- 費用は123,500円(登録免許税・登録手数料)かかる
- 特別国際種事業者の登録は行政書士に依頼することも可能
