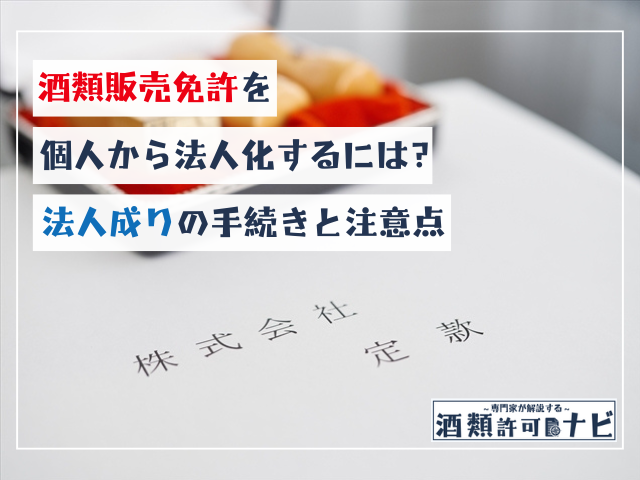

酒類販売免許で個人から法人成りするには?
個人の免許を使ったり法人名義に変更できる?

事業が軌道になり、個人から法人成りをしようと思った時に、上記のような疑問を抱える方も多いです。
結論から先にいうと、個人で取得した酒類販売免許は法人で使うことはできず、法人で新たに免許を取り直す必要があります。
また、個人から法人成りする際には注意点があるのですが、その注意点を知らずに手続きを進めてしまって、後々トラブルに繋がることも多いです。
そこで、この記事では酒類販売免許の専門家が、個人から法人成りする際の手続きの流れや注意点について解説します。
この記事を書いた人
個人で取得した酒類販売免許は法人化しても使える?
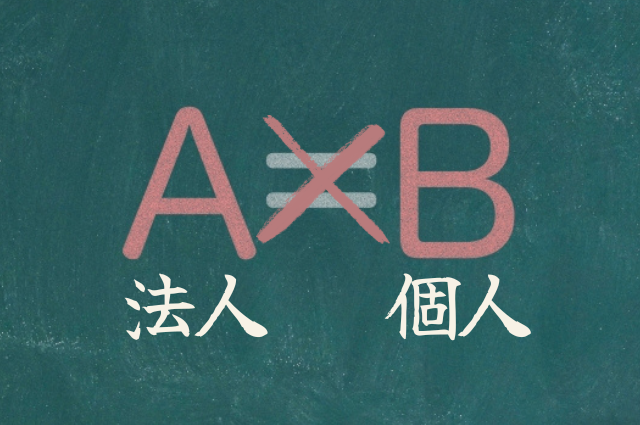
結論から言うと、個人で取得した酒類販売免許を、法人化した後にそのまま使うことはできません。
なぜなら、法人の代表者が個人事業主時代と同じ人物であっても、法律上は「個人」と「法人」は全くの別人物として扱われるからです。
例えば、鈴木太郎さんが個人事業主として「鈴木酒店」を経営し、鈴木太郎の個人名義で酒類販売免許を取得していたとします。
その後、事業拡大のために「株式会社スズキ」を設立し、鈴木太郎さんが代表取締役に就任した場合でも、「鈴木太郎」と「株式会社スズキ」は法律上は別の存在です。
そのため、個人で取得した酒類販売免許は法人化した後でも、個人の免許を引き続き使用することができません。
個人の酒類販売免許を法人で使った場合の罰則
もし、個人事業主時代に取得した免許を使って法人成りした後もお酒を販売した場合、法人は「無許可営業」と見なされて処罰の対象となります。
たとえば、先ほどの例でいうと、鈴木太郎の個人名義で取得した免許を使って株式会社スズキでお酒を販売した場合、株式会社ススキは無免許でお酒を販売していることになります。
そして、無許可でお酒を販売した場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、個人の免許を取り消される可能性や、罰則を受けた場合には3年間は酒類販売免許を取得することができないなどのリスクもあるので法人成りする際は注意が必要です。
個人で取得した酒類販売免許を法人名義に変更できる?

個人で取得した酒類販売免許を、後から法人名義に変更することはできません。
なぜなら、酒類販売免許は申請者である「個人」や「法人」といった“その人”に限定して与えられるものだからです。
たとえば、自動車の運転免許証を名義変更して別の人に免許を譲ることができないように、酒類販売免許も名義を変更して取得した免許を別の人の譲ることができないのです。
これは、個人事業主から法人成りし、個人がそのまま代表取締役を務める場合でも同じです。
そのため、法人成りの手続きとして、個人と免許の取消申請と合わせて法人で新たに免許を取得し直す必要はあります。(国税庁|お酒についてのQ&A-酒類製造・販売業免許関係(共通)Q2)
要件を満たせば免許の条件を引継げる
個人事業主が法人化する場合、原則として法人名義で新たに酒類販売業免許を取得する必要があると解説しました。
しかし、現在では新規取得が認められていないゾンビ免許(旧酒類販売免許)などで営業している人が法人化すると、従来と同じ形で営業を続けられなくなる可能性があります。
しかし、特定の要件を満たしている場合には、個人で取得した免許条件を引き継ぐことが認められています(国税庁の法令解釈通達(酒税法第9条1項関係)-14法人成り等の場合の酒類の販売業免許の取扱い)。
具体的には、以下の要件を全て満たす必要があります。
新設法人でも酒類販売免許の取得は可能
通常、法人で酒類販売免許を申請する場合、以下の書類を提出する必要があります。
となる、「会社を設立してから最低でも3年は経過していないといけないのでは?」と心配になる方も多いです。
しかし、結論から言うと、新設法人でも免許の取得は可能です。
そのため、個人から法人成りした新設した法人で酒類販売免許は取れるので安心してください。
酒類販売免許を個人から法人成りする際の注意点

酒類販売免許について、個人から法人成りする場合、法人で新たに酒類販売免許を取り直さなければなりません。
そして、法人成りで酒類販売免許を取り直す場合、新規で免許を取得する時とはことなり以下のような注意点があります。
個人の免許との切り替えタイミング
酒類販売免許は同じ販売場で複数の免許を取得することができません。
つまり、個人と法人の2つの免許を同じ場所で取得することができないというわけです。
となると、「個人免許の取消」と「法人免許の取得」を同時並行で進める必要があります。
そこで、重要となるのが税務署との綿密な打ち合わせです。
管轄の税務署にどのような手順で進めればいいかを相談しながら手続きをすすめることで、個人から法人免許にスムーズに切り替えが可能です。
逆に、適切な流れで「個人免許の取消」と「法人免許の取得」ができないと、お酒を販売できない期間が発生してしまうので注意が必要です。
賃貸物件の場合の契約名義人
これまで個人で結んだ賃貸契約契約書を法人名義に変更する必要があります。
酒類販売免許の申請では、販売場の使用権限が適切にあることを証明するため、賃貸契約書を提出するのですが、個人で契約を結んでいる賃貸契約書を提出しても、適切な使用権限があるとは見なされません。
これは、ここまでで何度も言っているように、法人と個人は全く別の存在として扱われるからです。
そのため、賃貸契約書の契約名義を変更するか、物件所有者から使用承諾書をもらうなどの対応が必要となります。
全ての役員が欠格事由に該当しない
個人で酒類販売免許を取得する場合、個人が欠格事由に該当しなければ酒類販売免許を取得することができました。
しかし、法人で酒類販売免許を取得する場合、代表者だけでなく、全ての役員が欠格事由に該当しない必要があります。
もし、役員のうち1人でも、欠格事由に該当する場合には、酒類販売免許を取得することはできません。
そのため、申請前に必ず全ての役員に欠格事由に該当しないかを確認する必要があります。
個人で抱えた酒類の在庫
酒類販売業者には、酒類の仕入・販売・在庫の状況を帳簿に記録する義務があり、免許の取消申請時にも現在の在庫状況を報告する必要があります。
具体的には、個人で保有していたお酒の在庫を法人成りした際にどのように処分するのかです。
処分方法には、仕入れ先への返品や廃棄処分、自家消費などがありますが、個人から法人成りする場合、個人の在庫を法人が引き継ぐケースが一般的です。
そのため、酒類販売免許の取消申請では、処分方法に「その他:法人成の個人が引く継ぐ」と記載すれば問題ありません。
個人から法人化する場合の酒類販売免許の取得の流れ

酒類販売免許を個人で取得していて、法人成りにする場合、以下のような流れで進めるとスムーズに個人から法人の免許に切り替えることが可能です。
STEP1:法人を設立する
酒類販売免許で法人成りをする場合、まず最初に法人を設立します。
法人を設立する際の注意点としては、法人の事業目的の中に酒類販売事業に関する目的を必ずいれることです。
具体的には、「酒類の小売、通信販売、輸出入および卸売業」というように、文言で追加しておけば大丈夫です。
STEP2:税務署に法人成りを相談する
法人成りする場合には、事前に税務署に相談に行くようにしましょう。
注意点のところでも解説しましたが、酒類販売免許は同じ場所で複数の免許を取得することができません。
そのため、個人の免許の取消申請と法人の新規取得申請の2つの手続きを並行して行わなければなりません。
この手続きが上手くできないと、お酒を販売できない期間が発生してしまうため、事前に税務署に相談しながら慎重に進めるようにしましょう。
STEP3:契約書等の名義変更手続きを行う
賃貸物件で酒類販売を行う場合、契約書が個人名義のままだと法人での免許申請が通らない可能性があります。
そのため、賃貸借契約を法人名義に変更するか、物件所有者から法人使用の承諾書をもらう必要があります。
ちなみに、名義変更せずに物件所有者から使用承諾書をもらって提出する場合には、物件借主である個人の使用承諾書も添付しなければならない点は注意が必要です。
STEP4:法人名義で酒類販売免許の申請をする
名義変更や税務署への相談が済んだら、いよいよ法人名義で酒類販売免許の申請を行います。
申請に必要な書類は、個人のときと似ていますが、法人登記簿謄本や定款、役員全員の履歴書など、法人ならではの書類が追加で求められます。
申請後は、通常およそ2か月の審査期間があり、審査が完了すれば税務署から許可の連絡が入ります。
STEP5:個人名義の免許取消申請をする
法人で新たに酒類販売免許を取得する場合、個人で持っていた免許を取り消す必要があります。
この手続きのタイミングが管轄の税務署によって若干異なりますが、法人の新規申請書と合わせて個人の取消申請書を提出するのが一般的です。
ただし、いつまで個人で営業するのかや、営業を辞めるタイミングでの在庫数量など、営業を辞めるタイミングでなければ記載が難しい項目も多いです。
STEP6:法人の許可証を受取る
個人の取消申請と法人の新規免許取得が上手くいけば、無事に法人の酒類販売免許を受け取ることができます。
因みに、個人の免許受け取り時に登録免許税を支払ったと思いますが、法人の免許受け取り時にも登録免許税を支払う必要があります。
免許の受け取りが完了すれば、その日から法人名義で酒類販売免許の営業が可能となります。
酒類販売免許で法人成りする場合のメリット・デメリット

ここまで、個人で取得した酒類販売免許から法人で酒類販売免許を取得する流れを解説してきました。
しかし中には、「そもそも法人りするべきなのか?」と迷っている方もいるかと思います。
そこで、酒類販売免許の取得において、個人から法人に切り替えるメリットとデメリットを簡単に触れておきます。
酒類販売免許で法人化するメリット
酒類販売免許を個人から法人に切り替えることで、上記のようなメリットがあります。
まず、法人にすることで「社会的な信用」が高まるのがメリットのひとつです。
法人は対外的にも信頼されやすくなるので、銀行とのやり取りや取引先との契約がスムーズになりやすく、これから事業を広げたい方にとっては大きな後押しになります。
また、個人に比べて法人の方が節税できる可能性が高いです。
たとえば、役員報酬の設定や経費の使い方など、法人ならではの税務の工夫ができるため、手元に残るお金を増やせるケースもあります。
さらに、法人では決算期を自由に決められるのもポイントです。
忙しい時期を避けて会計処理をしたり、納税のタイミングを調整したりと、経営のリズムに合わせやすくなります。
酒類販売免許で法人化するデメリット
一方で、酒類販売免許を個人から法人に切り替えることで、上記のようなデメリットもあります。
まず、設立時に費用がかかる点です。
法人を設立するには、登録免許税や定款認証費用などで30万円程度必要です。
また、法人を設立した場合、維持費も継続して掛かります。
例えば、顧問税理士への契約費用や、法人税などを毎年一定金額以上払わなければなりません。
つまり、法人成りすることで個人の時よりもコストがかかるため、売り上げが安定していない段階での法人成りはあまりおすすめしません。
酒類販売免許の法人成りをスムーズに進めたい方へ

ここまで酒類販売免許の個人から法人なりした際の切り替え手続きについて解説していきました。
法人成りによる酒類販売免許の取得は、免許の切り替え時期や契約名義人の変更など、新規で免許を取得する場合よりも注意しなければならない点も多いです。
しかも、手順を間違ってしまうと、お酒を販売できない期間が発生したり、無許可営業の繋がるリスクもあります。
そのため、個人から法人成りに伴う酒類販売免許の取得に関しては専門家に相談しながら進めるのが安心です。
酒類許可ナビ代行では、個人の取消申請やもちろんのこと、税務署とのやり取りや、法人の酒類販売免許取得についても徹底的にサポート致します。
既に、法人を設立してこらから酒類販売免許の申請をする方は、まだ法人の設立をしてない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
\まずはお気軽にご相談下さい/
▶酒類許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
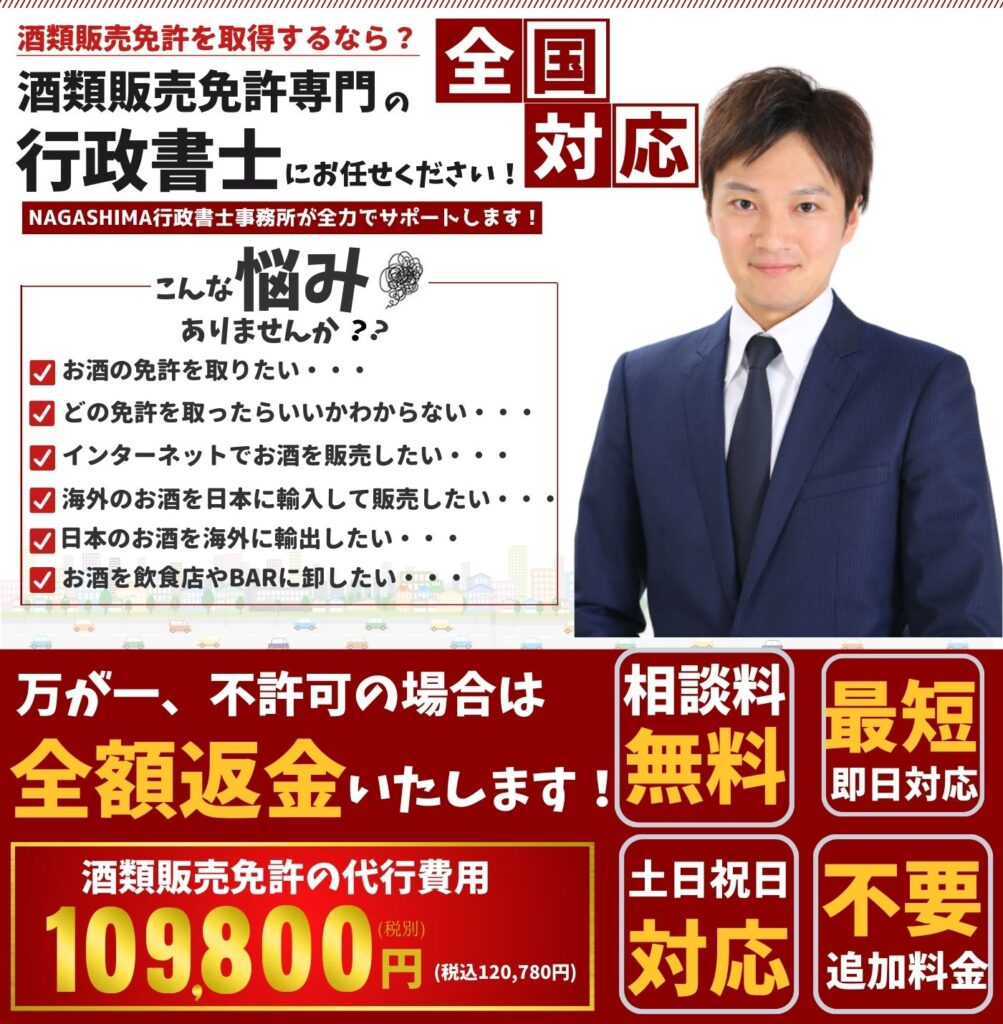

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- 個人の免許で法人がお酒を販売できない
- 個人の免許を法人名義に変更できない
- 法人成りする場合には新規で酒類販売免許の取得が必要
- 個人の免許取消申請と並行して手続きが必要

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所