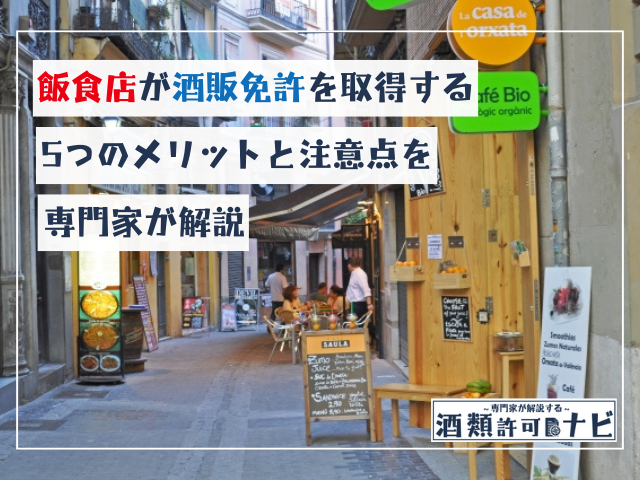

飲食店で酒販免許を取得するメリットって何?
飲食店が酒販免許を取得する上での注意点は?

といって疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
飲食店で酒販免許を取得すると主に5つのメリットがあるのですが、一方で注意しなければならない点もあります。
そこで、この記事では飲食店で酒販免許の取得を検討している方向けに、どんなメリットがあるのかや注意点について解説します。
この記事を書いた人
飲食店が酒販免許を取得する5つのメリット

飲食店で酒販免許を取得すると以下の5つのメリットがあります。
①売上・利益の最大化につながる
「一般酒類小売業免許」があれば、店内でのお酒の提供だけでなく、お酒をテイクアウト用に販売できるので、飲食代+αの収益が見込めるようになります。
たとえば、飲食したお客様に対してワインやクラフトビールなどの少し高いお酒をテイクアウト用として販売することで、客単価UPに繋がりやすいです。
また、ウーバーイーツなどのデリバリーサービスでもお酒を取扱えるようになるため、お店の外での売り上げについても売り上げを大きく伸ばすことが可能です。
②営業時間に縛られない収益源
酒販免許の中でも「通信販売酒類小売業免許」を取得すれば、ネットショップでお酒を販売できるようになります。
これにより、営業時間や店舗の立地に関係なく、24時間いつでも収益を上げることが可能になります。
たとえば、自社サイトやECモールを使えば、お店が閉まっている時間帯でもお酒が売れますし、遠方のファンやリピーターにも商品を届けることができます。
飲食店という枠を超えて「酒販店」としての顔を持つことで、収益の幅がぐっと広がり、時間や場所に縛られないビジネス展開が可能になります。
③差別化・ブランディング
酒販免許を取得すれば、OEMで自社ブランドのお酒を作って販売することも可能になります。
たとえば、自分のお店の料理に合うオリジナルのワインやクラフトビールを企画すれば、他にはない“ここだけ”の商品として打ち出すことができ、自然とブランディングにつながります。
しかも、自社ブランド商品であれば、原価率を抑えつつ高利益での販売が可能です。
「酒販ができる店」として認知されるだけでも、近隣の飲食店との差別化になりますし、特別感のあるお酒があることでお店の魅力や話題性もアップします。
④顧客満足度・リピート率アップ
「このお酒、美味しかったから家でも飲みたい」と思ったお客様に、その場でテイクアウト用として販売できるのは、酒販免許を持つ飲食店ならではのメリットです。
その場で気に入ったお酒を買って帰れると、お客様の満足度も上がりますし、「またあのお店に行こう」と思ってもらえるきっかけにもなります。
また、常連のお客様向けに限定銘柄や数量限定の販売を行うなど、ちょっとした“特別感”を演出することも可能です。
こうした細やかなサービスが顧客満足度をアップさせ、結果としてリピート率のアップにも繋がります。
⑤仕入れコストの最適化
酒販免許を取得すると、小売用のお酒を仕入れることが可能になり、飲食提供用よりも安く仕入れられるケースがあります。
また、販売量が増えることでスケールメリットが出やすくなり、仕入れ業者との取引条件が有利になる可能性もあります。
さらに、酒販免許を取得して独自の仕入れルートを開拓できれば、価格や品揃えの面でも他店と差をつけることが可能になります。
仕入れコストを抑えつつ、収益性を高められる点も、飲食店が酒販免許を取得する大きなメリットのひとつです。
飲食店が酒販免許を取得する際の注意点

飲食店が酒販免許を取得するメリットはたくさんありますが、取得に関しては注意点もあります。
それは、原則として飲食店では酒販免許は取得できないということです。
というのも、酒販免許を取得するには酒販免許の要件を全て満たさなければならないのですが、その要件の中に「申請場所が飲食店と同一の場所でないこと」があるからです。(国税庁|法令解釈-第10条 製造免許等の要件)
そのため、例えば、飲食店で通常の酒販免許の申請と同じように申請したとしても、許可を取得することはできません。
ただし、例外として免許の取得が認められるケースがある
飲食店では原則として酒販免許の取得は認められていませんが、例外もあります。
その例外とは、飲食店と酒類販売業の営業が明確に分けられている場合です。
飲食店と酒類販売業が分けられているかどうかの判断基準については、特定の条件を満たしているかどうかで判断されます。
特定の条件については次の項目でそれぞれ詳しく解説します。
飲食店で酒販免許を取るための条件

飲食店で酒販免許を取得するには、通常の酒販免許の要件に加え、以下の特定の要件を満たさなければなりません。
エリアを分ける
飲食店で酒販免許を取得する上で最も重要なのが、飲食スペースと酒類販売スペースを物理的に明確に分けることです。
例えば、飲食スペースとは別に個室を設け、その個室で酒類販売を行うような場合です。
一方で、どこからどこまでが飲食スペースで、どこからどこまでが酒販スペースか分からないような曖昧な区分の場合には、この要件を満たさないと判断されてしまう可能性があります。
保管場所を分かる
飲食店で提供するお酒と小売用に販売するお酒の保管場所についても物理的に分ける必要があります。
というのも、同じ場所に保管してしまうと、どのお酒が飲食用でどのお酒が小売用なのかが分からなくなってしまうからです。
例えば、飲食用のお酒はキッチンに保管し、小売業のお酒は倉庫に保管するといった形で分ける必要があります。
仕入れを分かる
飲食店が酒類販売業免許を取得して、お酒の販売を始める場合は、店内で提供するお酒と販売するためのお酒を別々に仕入れる必要があります。
というのも、飲食用のお酒は、一般の酒屋などの小売業者から仕入れるのに対し、小売用のお酒は卸売業者から仕入れなければならないと決まっているからです。
また、飲食用と販売用の両方に対応している業者(小売業免許と卸売業免許を持っている業者)から仕入れる場合でも、仕入れの目的ごとに注文や納品書をしっかり分けて管理する必要があります。
会計を分ける
飲食店でお酒を販売する場合、飲食用と小売用の会計を分ける必要があります。
例えば、飲食用のレジと小売業のレジを分けたり、商品コードを分けたりと、同じ商品でも飲食用と小売業で区別する必要があります。
特に、小売については消費税が8%なのに対して、飲食用のお酒は消費税が10%と税率が異なるため、混同しないように注意が必要です。
帳簿を分ける
最後に、帳簿の記載についても飲食用と小売用で分ける必要があります。
店内で提供するお酒は飲食業としての扱いになる一方、持ち帰り用やデリバリーで販売するお酒は「小売」として別の業種となるため、それぞれの取引内容を明確に区分して記録しておく必要があります。
たとえば、飲食スペースで提供するビールやワインの売上は飲食業の帳簿に、テイクアウト用として販売したワインやクラフトビールの売上は酒類販売業の帳簿に記載する、といった形で管理を分けるのが基本です。
こうした区分ができていないと、税務署から「事業が明確に分けられてない」と判断される可能性もあるため注意が必要です。
飲食店で酒販免許を取得するなら行政書士に相談

ここまで記事を読んだ方の中には、メリットが多いし飲食店で酒販免許を取得したいと思った方も多いと思います。
ただし、飲食店で酒販免許を取得するには、通常の申請とは異なる注意点や条件が多く、専門的な知識が求められます。
そのため、飲食店で申請をするなら酒類販売許可ナビ代行に相談することをおすすめします。
酒類販売許可ナビ代行では、店舗の構造や営業スタイルに合わせて、どのように要件をクリアすればよいかを具体的に提案や、書類作成、税務署とのやり取りも全て任せることができます。
もちろん、「まずは話だけ聞いてみたい」「自分のお店で取れるかだけ知りたい」といった軽いご相談でも大丈夫です。
無理に契約をすすめることもありませんので、気になる方はお気軽にご連絡ください。
あなたのお店に合った、最適な取得プランをご提案します。
\まずはお気軽にご相談下さい/
▶酒類許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
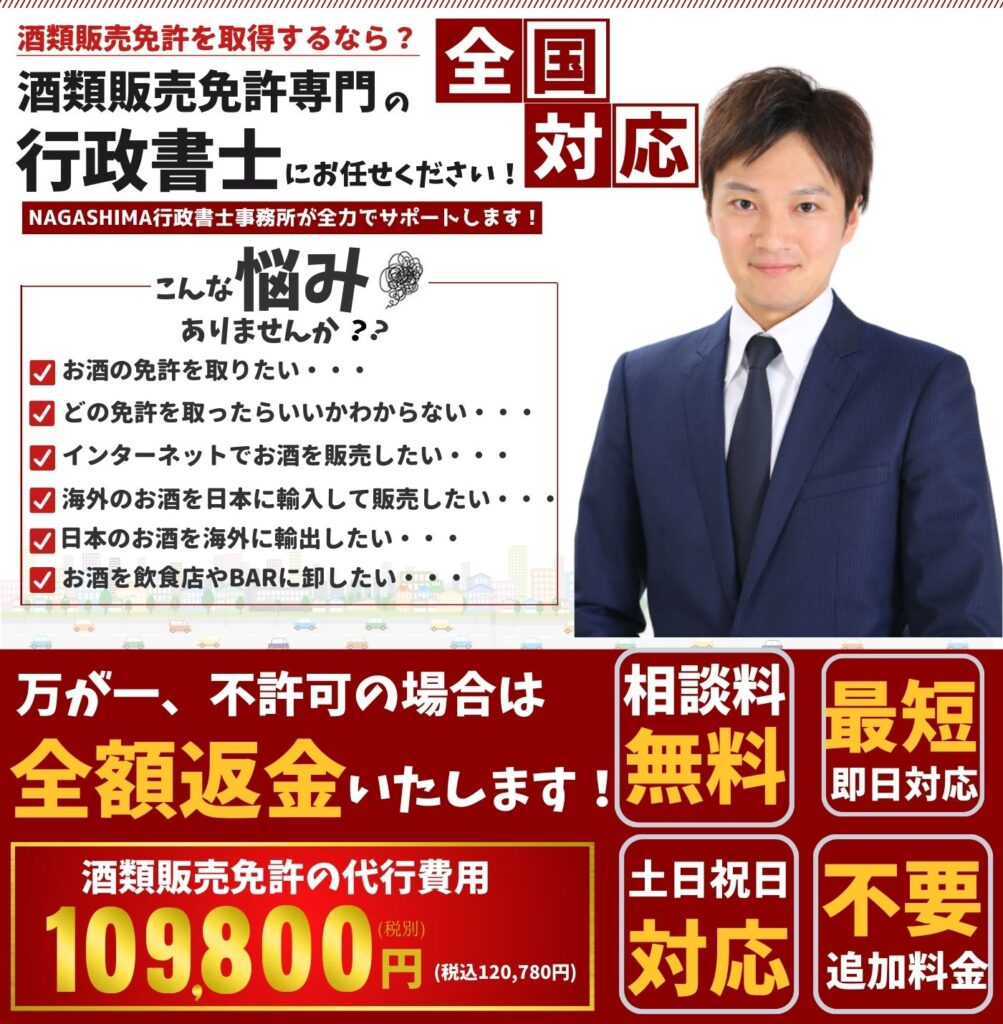

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- 飲食店で酒販免許を取ると売上・利益UPに繋がる
- 飲食店で酒販免許を取ると営業時間に縛られない収益源ができる
- 飲食店で酒販免許を取ると差別化・ブランディングできる
- 飲食店で酒販免許を取ると顧客満足度・リピート率UPに繋がる
- 飲食店で酒販免許を取ると仕入れコストの最適化に繋がる

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所