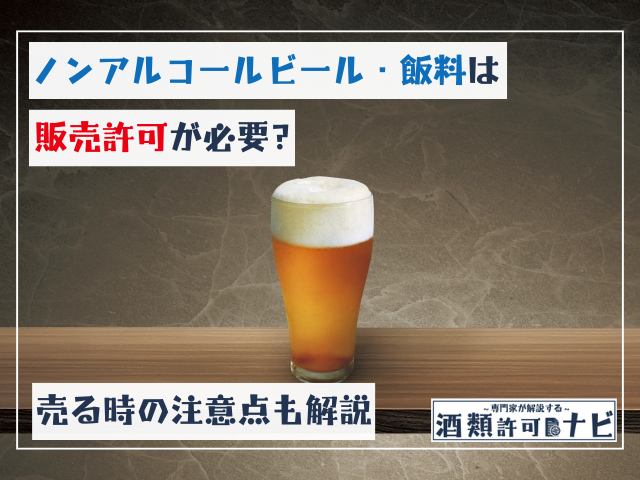

ノンアルコールビールやノンアルコール飲料を売るのに許可って必要?
飲食店でノンアルコールビールを提供するのに特別な許可が必要?

ノンアルコールビールやノンアルコール飲料を販売したり、飲食店で提供しようと思った時に、上記のような疑問を抱えている方も多いです。
結論から先にいうと、ノンアルコールビール・飲料を販売したり、飲食店で提供する場合、特別な許可は不要です。
しかし、ノンアルコールビール・飲料を取扱う場合には注意しなければいけないこともあるのですが、それを知らずに販売・提供してしまっている方も多いです。
そこで、この記事ではこれからノンアルコールビール・飲料の取り扱いを検討している方向けに許可の必要性や注意点について分かりやすく解説します。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
この記事を書いた人
ノンアルコールビール・飲料の販売に許可は必要?

ビールや焼酎、ワインなどのお酒を販売するには、酒類販売免許が必要です。
ですが、ノンアルコールビールやノンアルコール飲料を販売する場合には、特別な許可は必要ありません。
というのも、ノンアルコールビールやノンアル飲料は、法律上はジュースなどのソフトドリンクと同じような扱いになるからです。
つまり、ジュースを販売するのに許可がいらないのと同じように、ノンアルコール飲料を売るときも許可はいらないということになります。
(因みに、ジュースと同じような扱いではありますが、厳密には若干異なります。詳しくは、後程紹介するノンアルコールビール・飲料を売る時の注意点で解説します。)
そのため、ノンアルコールビール・飲料はコンビニやスーパーでの店頭販売はもちろん、Amazonや楽天などのネット通販、さらにはイベントやキッチンカーでの移動販売といった形でも、許可なく販売することが可能です。
そもそもノンアルコールとは?
ノンアルコールとは、アルコール分が1%未満の飲料のことを言います。
なぜ「1%未満」なのかというと、酒税法ではアルコール分が1%以上の飲料を「酒類」として定義しているためです。(酒税法2条)
この基準により、アルコール分が1%未満のノンアルコール飲料は、法律上お酒ではなく、ソフトドリンクのような扱いになるのです。
そのため、ビール風味やチューハイ風味のノンアル飲料でも、アルコール度数が1%未満であれば、酒類販売免許なしで販売できます。
飲食店でノンアルコールビール・飲料を提供するのに許可は必要は?

結論から言えば、飲食店でノンアルコールビールやノンアルコール飲料を提供するのに、酒類販売免許は必要ありません。
お酒の小売りと同様に、飲食店での提供でも、ノンアルコール飲料は法律上「酒類」にはあたらないため、特別な許可を取る必要がないのです。
たとえば、ノンアルコールビールをグラスに注いで提供したり、ノンアルコールカクテル(モクテル)をオリジナルメニューとして出したりする場合でも、アルコール度数が1%未満であれば、問題ありません。
また、お酒のテイクアウト販売には酒類販売免許が必要になりますが、ノンアルコール飲料であれば、持ち帰り販売を行う場合でも許可を取る必要はありません。
店内での提供に限らず、ボトルでの販売やデリバリーでも、他のソフトドリンクと同じ対応が可能です。
そのため、居酒屋やカフェ、レストランなどでも、ノンアルコール飲料を自由にメニューに加えたり、持ち帰り商品として販売したりすることができます。
ノンアルコールビール・飲料を売る時の注意点

ノンアルコールビールやノンアルコール飲料は、法律上「酒類」に該当しないため、販売や提供に許可は必要ありません。
しかし、販売方法や対象者、陳列の仕方によっては誤解やトラブルを招くおそれがあるため、注意すべきポイントがいくつかあります。
具体的には以下のポイントに注意して取扱うようにしましょう。
アルコールが含まれているノンアルもある
「ノンアルコール」と聞くと、アルコールが一切含まれていないと思われがちですが、実は微量のアルコールが含まれている商品もあります。
たとえば、ノンアルコールビールの中にはアルコール度数0.5%のものもあり、法律上は酒類にあたらないものの、体質や飲む量によっては体内にアルコールが残る可能性があります。
特に気をつけたいのは、短時間に大量に飲んだ場合です。
状況によっては、呼気中アルコール濃度が酒気帯び運転の基準を超えてしまう可能性も0ではありません。
そのため、こうしたリスクを避けるためにも、飲食店でノンアルコール飲料を提供する際は、アルコール度数が0.00%の完全ノンアルコール商品を選ぶのが安心です。
20歳未満の方への販売は推奨されていない
ノンアルコール飲料は、アルコール度数が1%未満であれば法律上は「酒類」に該当せず、20歳未満の未成年者が飲むこと自体に法的な制限はありません。
ただし、多くのメーカーは20歳以上の大人を主なターゲットとして商品を設計しており、パッケージにも「未成年の飲用はお控えください」といった表記がされていることが一般的です。
また、ノンアルコールとはいえ見た目や味が本物のお酒に近いため、未成年者の飲酒への興味を助長したり、将来的な飲酒習慣や依存リスクにつながる可能性もあると指摘されています。
そのため、法律上は20未満の方がノンアルコールビール・飲料を飲んでも問題ありませんが、20歳未満への販売はあまりおすすめはしません。
ちなみに、年齢確認が義務付けられているわけではありませんが、店舗によっては独自に年齢確認を実施したり、未成年者への販売を控える対応を取っていることもあります。
酒類と間違わないように店頭で陳列
ノンアルコールビールやノンアルコール飲料には、見た目やデザインが本物のビールやチューハイと非常によく似ている商品も多いです。
そのため、店頭で酒類と並べて陳列していると、「ノンアルだと思って手に取ったら実はアルコール入りだった」という誤認が生じる可能性があります。
たとえば、未成年者がパッと見た印象で「ノンアルコールだ」と思い込み、実際にはアルコールを含む商品を購入してしまうと、意図せず飲酒につながるおそれがあります。
また逆に、大人が「お酒だと思って買ったのに、実はノンアルだった」と気づかず購入してしまい、トラブル繋がる可能性もあります。
こうした誤解を防ぐためにも、ノンアルコール飲料は酒類としっかり分けて陳列し、「アルコール0.00%」「ノンアルコール」などの表示が明確に見えるようにするようにしましょう。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
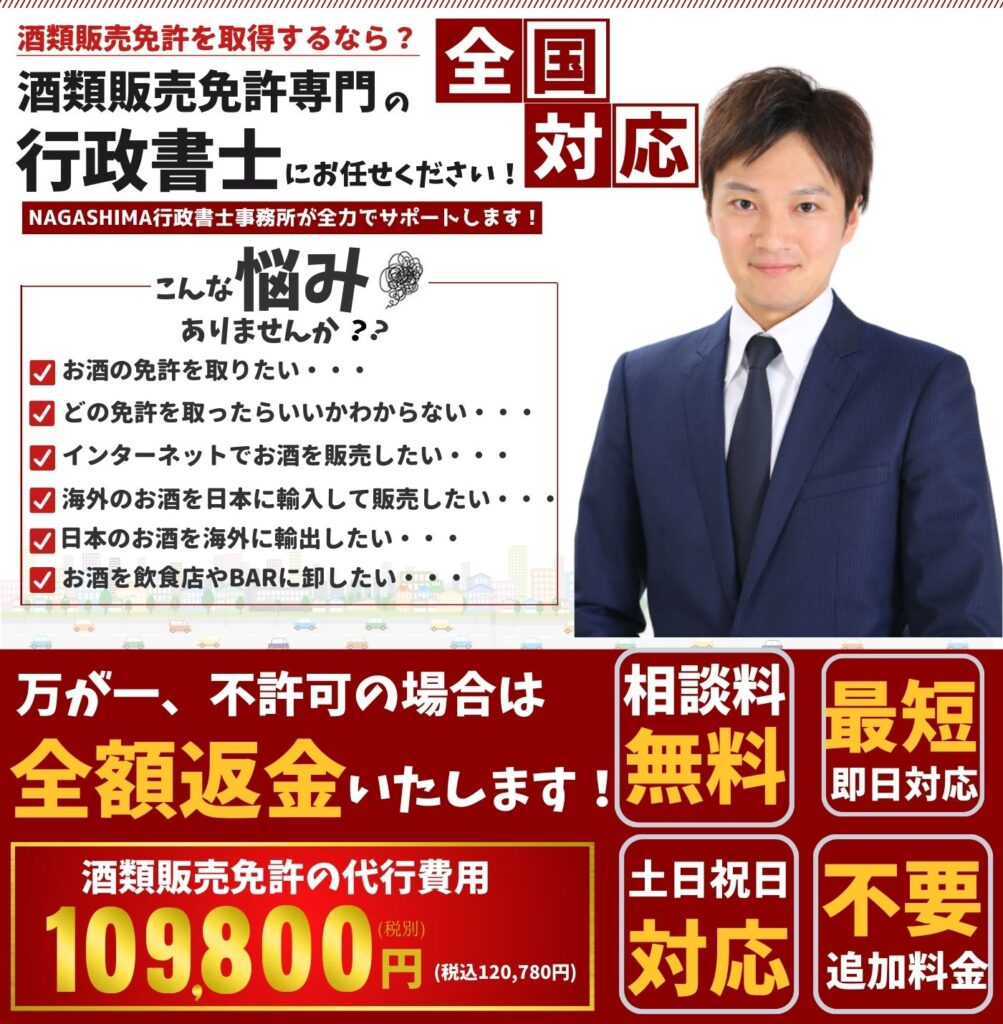

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- ノンアルコールビール・飲料や許可がなくても販売できる
- ノンアルコールビール・飲料は許可なしに飲食店で提供やテイクアウトも可能
- ノンアルコールビール・飲料は微量のアルコールが含まれている商品もあるので注意
- 飲食店でノンアルコールビール・飲料を出す場合にはアルコール0%の飲料を選ぶ

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所