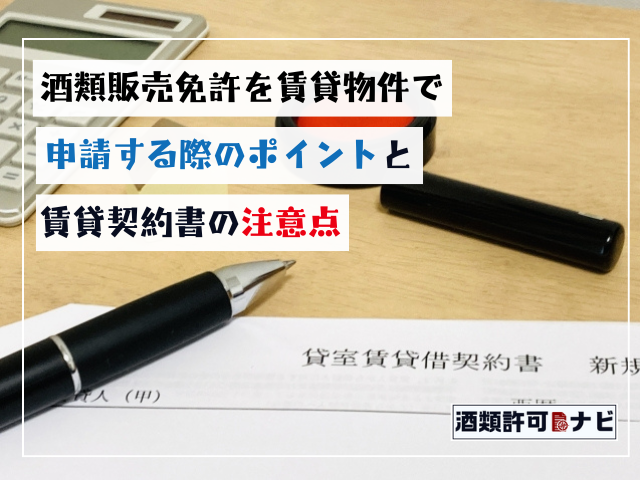
賃貸物件で酒類販売免許を取得したいけれど、どんな点に注意したらいいんだろう…


契約内容に制限がある場合、どう対処すればいいの?
賃貸物件で酒類販売免許を申請する場合、販売場の使用権限を証明するために賃貸契約書の提出が必須ですが、内容に不備があると申請がスムーズに進まないことも多いです。
ただ、そもそも賃貸契約書の内容を確認して、お酒の免許を取得できるかどうかを、法律にあまり詳しくない方が自分で判断するのは難しいです。
そのため、当サイト(酒類許可ナビ)では、営業所が免許の取得が可能かどうか無料で診断致します。
もし、これから酒類販売免許を取得して、お酒を販売したいと考えている方は、ぜひ、ご活用ください。
\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/
▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。
ただ、中には専門家にわざわざ相談して確認するのはハードルが高いと感じる方もいるかと思います。
そこで、本記事では、酒類販売免許の審査でチェックされるポイントや、契約内容に問題があった場合の対策について分かりやすく解説します。
この記事を書いた人
賃貸物件で酒類販売免許を申請する場合には賃貸契約書が必要
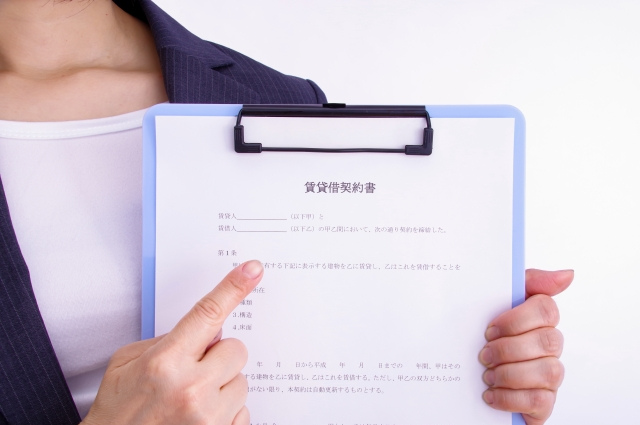
酒類販売免許を取得するには、必ず販売場を設置することが必要です。
そして、申請する販売場の土地や建物等が賃借物件の場合には、賃貸契約書のコピーを添付する必要があります。(国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」P40)
なぜなら、税務署の審査では、申請者が販売場の建物を確実に使用できることを「賃貸契約書」で確認するためです。
また、酒類販売業免許の要件として、「酒類を継続的に販売するための販売施設を有していること」(経営基礎要件)が求められており、その証明としても必要になります。
一方で、販売場が自己所有物件である場合は、賃貸借契約書の提出は不要です。
ただし、戸建てやマンションなどの建物が登記上自己所有であることを証明するため、不動産の登記事項証明書のは提出しなければなりません。
酒類販売免許における賃貸契約書のチェックポイント

税務署は、申請者が販売場として使用する賃貸物件を、適法に使用する権限を持っているかどうかを審査します。
そのため、賃貸借契約書の記載内容で適正な使用権限を証明することが出きるかが重要となります。
特に以下のポイントを事前に確認し、該当する場合は追加書類の準備しなければならないケースもあります。
賃貸契約書の借主と申請者が一致しているか
酒類販売免許の申請では、賃貸借契約書に記載されている「借主」と申請者が一致していることが求められます。
契約上の借主と申請者が異なる場合、申請者が販売場を適法に使用する権限を持っているか確認できないため、追加書類が必要です。
特に以下のようなケースでは、借主と申請者が一致していないと判断されるため注意してください。
- 法人が申請者で、物件の借主が代表取締役個人である場合
- 申請法人と同じ代表取締役が経営する別法人が借主の場合
- 賃貸部件を借りている知人から又貸ししてもらっている場合
上記の場合には、法律上は借主が申請者に転貸しをしていることになります。
貸主と登記簿上の所有者が一致しているか
酒類販売免許の申請では、賃貸借契約書に記載されている貸主と、不動産の登記簿上の所有者が一致しているかが確認されます。
そして、貸主と登記簿上の所有者が一致していない場合には、別の書類を追加で提出する必要があります。
なぜなら、登記事項証明書と賃貸契約書だけでは、申請者が販売場を適法に使用する権限を持っているか確認できないからです。
例えば、不動産所有者Aが不動産の運営・管理を不動産会社Bに任せていたとします。
この場合、基本的にはBと賃貸契約を結ぶことになるのですが、Bとの賃貸契約書だけでは本当にAがBに不動産の運営・管理を任せているのは判断できません。
そのため、Bが適切な使用権限を持っていることを証明する書類か、Aから直接承諾を受けていることを証明する書類が必要となります。
「使用目的」や「使用用途」違反になる
酒類販売免許の申請では、賃貸借契約書に記載されている「使用目的」や「使用用途」が、酒類販売業の営業に対応しているかが重要な審査ポイントになります。
契約内容によっては、酒類販売業の使用が制限されている場合があるため、事前に確認が必要です。
具体的には、使用目的・使用用途が以下のように記載されている場合には注意が必要です。
- 「居住用」や「住居専用」と記載さがある
- 「〇〇業に限る」と用途が限定されている
- 「飲食店専用」や「小売業禁止」などの記載がある
もし、上記のような記載がある場合には、契約上はその場所で酒類の販売が認められていないことになるからです。
転貸(又貸し)や使用目的等が不十分の場合の対策

基本的には、不動産の登記事項証明書と賃貸契約書を提出すれば、販売場の適切な使用権限があることを証明できます。
しかし、中には不動産登記簿と賃貸契約書を提出するだけでは、適切な使用権限を証明できないケースもあるかと思います。
ここでは、以下の具体例について必要な対策を紹介します。
転貸・又貸し物件の場合の対策
申請者が直接物件を所有者から借りているのではなく、第三者から転貸されている場合、賃貸借契約書だけでは販売場の適切な使用権限を証明できません。
この場合、国税庁の手引きには以下のように記載されています。
賃貸借契約書等(申請販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類)の写し(転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写し)を添付してください。
引用:国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」P40
つまり、転貸や又貸しの場合には、「所有者と借主との賃貸契約書」、「借主と申請者との賃貸契約書」のコピーを提出する必要があるわけです。
例えば、不動産所有者Aから借りているBが、Aに転貸を禁止されているにも関わらず、Cに不動産を貸していた場合、Cは適切な使用権限があるとは言えないからです。
そのため、この場合にはBとCとの賃貸契約書だけではなく、AとBとの賃貸契約書も合わせて提出する必要があります。
ただ、多くの場合、所有者と借主との賃貸契約書を取得することが難しいケースも多いです。
なぜなら、いくらで借りた物件をいくらで貸しているかなどの事業経営における重要な情報が記載されているからです。
もちろん、契約料等の知られたくない部分を黒塗りにして提出してもらっても問題ありません。
しかし、それでは手間がかかる上に、申請者は物件を貸してもらっている立場なので、大元の契約書のコピーが欲しいとお願いすることすらハードルが難しいです。
そのため、国税庁の手引きでは「転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写し」を求められていますが、別の書類で対応が可能なケースもあります。
この点は、管轄の税務署によって若干対応が異なるので、個別ケースごとに税務署や行政書士などに相談することをおすすめしおます。
使用目的・使用用途に制限がある場合の対策
賃貸借契約書に「居住専用」や「〇〇業に限る」と記載されている場合、そのままでは酒類販売免許の申請は通りません。
しかし、不動産の所有者や管理会社から「酒類販売業として使用することの使用承諾書」を取得すれば問題ありません。
また、自己所有等のマンションの場合には、マンションの管理規約などで事業を禁止されているケースがほとんどです。
そのため、自己所有のマンションで酒類販売免許を取得する場合には、マンションの管理組合から使用承諾書を取得する必要があります
使用承諾書について詳しくは「使用承諾書とは?」の記事をご確認ください。
\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/
▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。
賃貸契約書がない場合にはどうすればいい?

酒類販売免許の申請では、販売場の適法な使用権限を証明するために賃貸借契約書の提出が求められます。
しかし、以下のようなケースでは契約書が手元にないことがあります。
- 口頭契約で書面を交わしていない場合
- 契約書を紛失してしまった場合
- 代表取締役や家族所有で契約を結んでいない場合
このような場合、そのままでは申請ができないため、以下の対策を取る必要があります。
口頭契約で書面を交わしていない場合
口頭契約で書面を交わしていない場合は、簡易的な契約書を作成するようにしましょう。
冒頭でも説明しましたが、酒類販売免許の取得には「酒類を継続的に販売するための販売施設を有していること」が求められます。
となると、口頭で契約を交わしているだけでは、本当に継続的にその場所を販売場と使用できるのかの確認ができません。
そのため、簡易的な契約書で構わないので、継続的にその場所を使用できることがわかる内容の契約書を作成し、提出するようにしましょう。
契約書を紛失してしまった場合
過去に契約したが、契約書を紛失してしまった場合には、契約書を再発行してもらうか、原本のコピーをもらうと良いです。
多くの場合、賃貸契約書は貸主と借主に1部ずつ原本を保管できる形で作成されるのが一般的です。
つまり、借主が契約書を紛失してしまったとしても、貸主の契約書は存在します。
そのため、貸主にお願いして原本をコピーしてもらうようにしましょう。
もちろん、契約書の原本を再発行してもらったり、新たに契約書を巻きなおすという方法もありますが、その場合だと追加で多くの費用が発生してしまう可能性があるので注意が必要です。
代表取締役や家族所有で契約を結んでいない
代表取締役や家族名義の物件を事業で使用する場合、契約書を結んでいないケースが多いです。
一般常識的に考えると、適切に使用する権限があることはわかりますが、酒類販売免許の申請では書類により使用権限を証明しなければなりません。
そのため、代表取締役や家族名義の物件を酒類販売場として申請する場合には、以下のうちのどれかを選択する必要があります。
- 賃貸契約書を作成しコピーを提出する(有料で貸す場合)
- 使用貸借契約書を作成しコピーを提出する(無料で貸す場合)
- 使用承諾書を作成し提出する
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
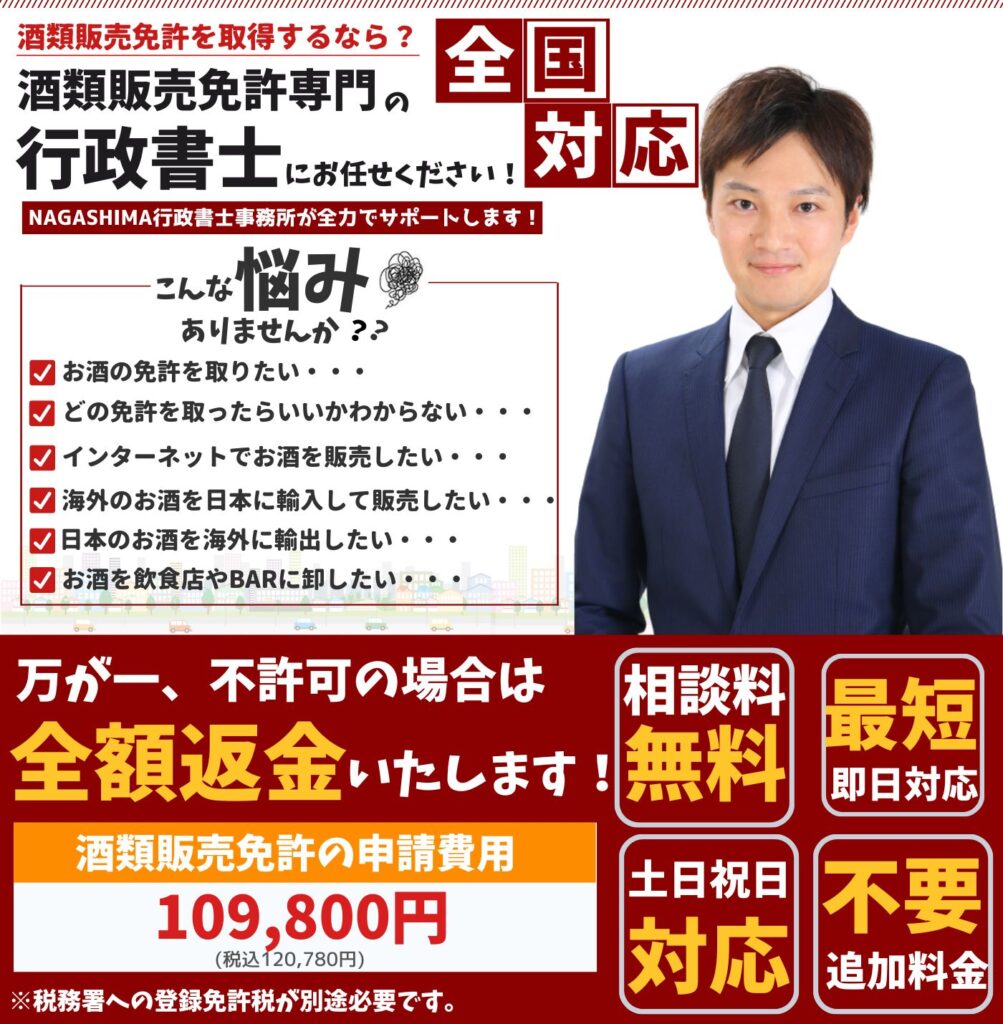

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- 賃貸物件で申請する場合には賃貸契約書の提出が必要
- 賃貸契約書の貸主・借主・使用用途・使用目的を確認する
- 転貸(又貸し)の場合には大元の契約書も必要
- 代表取締役や家族所有の物件でも書面で使用権限の証明が必要

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所