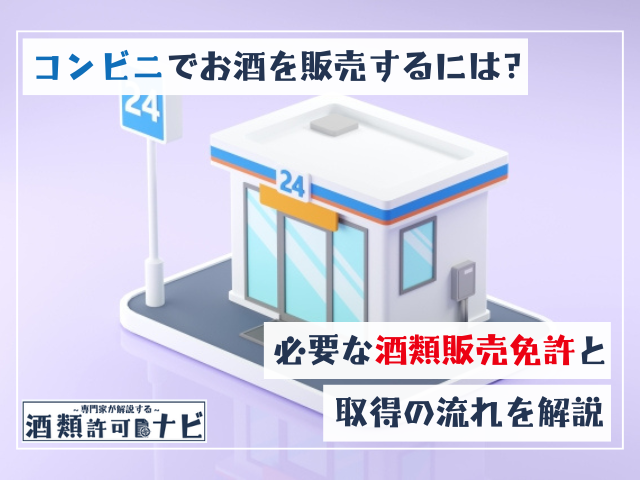

コンビニでお酒を販売するにはどの免許が必要?
コンビニでお酒を売る免許の取得の流れを知りたい

といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
コンビニでお酒を販売するには「一般酒類小売業免許」を取得しなければならないのですが、免許を取得するには色々と注意しなければいけない点も多いです。
また、免許の取得には準備段階を含めると3~4カ月程度かかるため、早い段階から手続きを進めておく必要があります。
この記事では、酒類販売免許の専門家がコンビニでお酒を販売する際に必要な免許を取得する上での注意点や、免許を取得する流れについて分かりやすく解説します。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
この記事を書いた人
コンビニで酒類を販売するには免許が必要?

結論からいうと、コンビニで酒類を販売するには、原則として酒類販売免許の取得が必要です。
しかも、全国展開している大手フランチャイズチェーンの店舗であっても、酒類の販売を行う場合は「その店舗ごと」に免許を取得しなければなりません。
例えば、ローソンやファミリーマート、セブンイレブンなどの店舗を出店する場合、その店舗で独自に酒類販売免許を取る必要があります。
そして、もし、仮に免許を取得せずにお酒を販売した場合に、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。(酒税法第56条)
コンビニが取るべき一般酒類小売業免許とは?
酒類販売免許には、以下のように色々な種類の免許があります。
そして、その中でもコンビニでお酒を販売する場合に、「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。
一般酒類小売業免許とは、一般の消費者に対して店頭で色々な種類の酒類を販売できる免許です。
ビールやワイン、日本酒、チューハイ、焼酎など、幅広い酒類を取り扱えるのが特徴で、酒類を販売しているほとんどのコンビニがこの免許を取得しています。
一方で、間違って一般酒類小売業免許以外の免許を取得してしまった場合には、たとえ許可を取得できたとしてもコンビニでお酒を販売することができないので注意が必要です。
コンビニが酒類販売免許を取得するための4つの要件

コンビニで酒類を販売するには、「一般酒類小売業免許」を取得するための4つの要件をすべて満たす必要があります。
基本的に、フランチャイズ本部が管理する標準的なコンビニ店舗であれば、これらの要件をクリアしているケースが多いですが、例外もあるため事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
以下では、酒類販売免許の4つの要件について解説しまう。
要件1:人的要件
人的要件とは、過去に法令違反等を犯していないかです。
具体的には、以下に該当する場合に人的要件を満たしていないと判断されます。
人的要件
- 過去に酒類販売やアルコール事業の免許を取り消されたことがある人
- 2年以内に税金の滞納処分を受けたことがある人
- 過去3年以内に税金や酒類販売に関する法律違反で罰金を受けた人
- 20歳未満にお酒を提供したり、暴力行為で罰金を受けた人
- 過去3年以内に拘禁刑以上の刑を受けた人
要件2:場所的要件
場所的要件とは、お酒を販売する場所として適切かどうかです。
具体的には、以下のような場合に場所的要件を満たさないと判断されます。
場所的要件
- 他の酒類販売店や飲食店と同じ場所
- 他の店舗と明確に区切られていない場所
ただし、コンビニの場合は、基本的に専用の店舗として運営されており、これらのケースに該当することはほとんどありません。
そのため、コンビニで酒類販売免許を取得する際には、場所的要件についてそこまで気にしなくても大丈夫です。
要件3:経営基礎要件
経営基礎要件とは、お酒を販売するために安定してコンビニを経営することができるかです。
具体的には、以下のような場合には、コンビニを安定的に経営できないと判断され、お酒の免許を取得できません。
経営基礎要件
- 破産していて、まだ復権していない場合
- 現在、税金を滞納している場合
- 過去1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 経営状態が悪化している場合
- 酒税法などの法律違反で罰を受け、処分が完了していない場合
- お店の場所が法律や条例に違反している場合
- 酒類の販売知識や経営能力が十分にない場合
- お酒を販売するための資金や設備、販売能力が不足している場合
ただし、これらの条件はあくまでも「新たに酒類販売免許を申請する場合」に求められる要件です。
つまり、すでに別の店舗で酒類販売免許を取得していて、新たに別の場所でコンビニを出店し、その店舗でも免許を申請する場合には、例外的に上記のような条件に該当していても許可を取得することができます。
要件4:需給調整要件
需給調整要件とは、新たに酒類販売業者を増やすことで酒類の需給バランスが崩れないかです。
具体的には、以下の内容について判断されます。
人的要件
- 申請者が過去に酒類や調味食品の販売・製造等に3年以上携わっているか
- 別業種での経営経験がある場合は、「酒類販売管理者研修」を受講しているか
- 継続的に酒類を販売できるだけの資金力・販売能力・店舗設備を備えているか
ただし、フランチャイズ本部のサポート体制や教育制度が整っており、実務研修を受けたうえで適切に販売管理を行える体制が整っていると判断されることが多いため、コンビニの場合はこの要件を満たさないと判断されるケースはほぼありません。
とはいえ、これまでに酒類販売経験がなかった場合に、酒類販売管理研修は受けるようにしましょう。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
コンビニで酒類販売免許を取得するまでの流れ
コンビニでお酒を販売するために一般酒類小売業免許を取得する場合、取得までの流れは以下のようになります。。
上記はが酒類販売免許の基本的な流れになりますが、酒類販売免許の申請には、たくさんの書類を作成したり、必要書類を収集しなければなりません。
しかも、1つ1つに細かい決まりがあり、記入ミスや書類の不足があると、修正や再提出が必要で取得までにかなり時間が掛かってしまします。
そうなると、コンビニの場合にはオープン日に間に合わない可能性があるので、心配な方は専門家に依頼することをおすすめします。
酒類許可ナビ代行では、税務署とのやり取りや書類の作成、必要書類の収集まで、全て丸投げできるので、依頼者様はコンビニの開店準備集中して頂けます。
コンビニで酒類販売免許を取得する際の注意点

特に、コンビニで酒類販売免許を取得する場合には、以下の点に注意してください。
取得までにかかる期間
酒類販売免許は、税務署に申請してから許可が下りるまでにおおよそ2か月程度かかります。
ただし、申請書の不備や添付書類の不足があると、さらに審査期間が延びてしまうため注意が必要です。
書類の準備や申請書の作成にかかる時間も含めると、スムーズに進めるためには最低でも3〜4か月前から準備をはじめたいところ。
コンビニの開店日に間に合わせたい場合には、余裕をもったスケジュールで進めるようにしましょう。
フランチャイズ契約の名義
酒類販売免許の申請では、申請者とフランチャイズ契約書・賃貸契約書などに記載された名義が一致している必要があります。
たとえば、免許の申請者が酒類許可ナビ株式会社であれば、フランチャイズ契約や店舗の賃貸契約も酒類許可ナビ株式会社である必要があります。
そのため、法人設立前に個人名義で契約を結んでいて、法人成して新たに免許を申請する場合には、そのままでは申請が通らない可能性もあるので要注意です。
名義等が異なる場合には、事前にどのような対応が必要なのか管轄の税務署に相談しましょう。
酒類販売管理者の選任
コンビニでお酒を販売する場合は、その店舗に必ず1人、酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、店舗でのお酒の販売に関して、ルールやスタッフへの指導を行う責任者です。
基本的には、この管理者が店舗に常駐している必要があります。
ただし、コンビニのように24時間営業の店舗では、常に管理者がいるのは現実的ではありません。
そこで、酒類販売管理者が不在の時間帯でも販売ができるよう、「販売管理者に代わる責任者」を選任することで対応が可能になります。
ちなみに、この販売管理者に代わる責任者は、研修を受講した酒類販売管理者と同程度の知識までも求めるものではないとされているので、販売研修を受けなていない人でも大丈夫です。(国税庁「酒類販売管理者制度に関するQ&A」問13)
また、パートやアルバイトの人が販売管理者に代わる責任者になることも可能です。
店舗ごとに酒類販売免許を取得
例えば、ローソンを出店する場合、他のローソンやローソンの本部が酒類販売免許を持っていても、店舗独自で免許を取得しなければお酒を販売することはできません。
しかも、たとえ同じ法人が経営するコンビニであっても、店舗の場所が異なるのであれば、それぞれの店舗について個別に免許を取得する必要があります。
というのも、酒類販売免許は、「各店舗ごと」に取得しなければならないからです。
つまり、仮に既に1店舗目で酒類販売免許を取得していても、2店舗目でお酒の免許を取得していないのであれば、2店舗目ではお酒を販売することはできません。
もし、販売した場合には無免許での販売となるので、酒税法違反により罰則を受けるだけでなく、1店舗目の免許も取り消される可能性があるので注意が必要です。
詳しくは「酒類販売免許は店舗ごとに必要?複数店舗展開時の注意点を解説」の記事で解説しているので、気になる方は合わせてチェックしてみてください。
20歳未満の飲酒防止の対策
酒類を販売する店舗では、20歳未満への販売を防ぐための対策が法律で義務づけられています。
コンビニでも、他の商品と酒類売場を明確に区切る必要があり、パーテーションや間仕切りなどで視覚的にわかるように分けて販売する必要があります。
また、酒類の陳列棚には「酒類コーナー」であることや、「20歳以上であることを確認できない場合には販売しません」といった注意書きを、表示基準に従って掲示しなければなりません。
なお、20歳未満の人が飲むと知りながら酒類を販売した場合には、販売者に50万円以下の罰金が科されることもあるため、従業員に対して年齢確認の重要性や販売ルールをしっかり教育しておくことが大切です。
コンビニでの酒類販売免許の取得が心配なあなたへ

コンビニのオープン準備はやることが多く、慣れない酒類販売免許の手続きまで並行して行うのは大きな負担です。
特に酒類販売免許は、作成・収集すべき書類が多く、細かいルールや決まりも多いので記載ミスや書類の不足を税務署から指摘されることも多いです。
そのため、申請がスムーズに進まないと、開店日までに許可が下りないリスクもあります。
「本当に間に合うだろうか…」「忙しいしなれない申請は専門家に任せたい」という方は、ぜひ、酒類許可ナビ代行にご相談下さい。
弊所では、申請書の作成から書類収集、税務署とのやり取りまで全て丸投げで酒類販売免許の取得をサポート致します。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
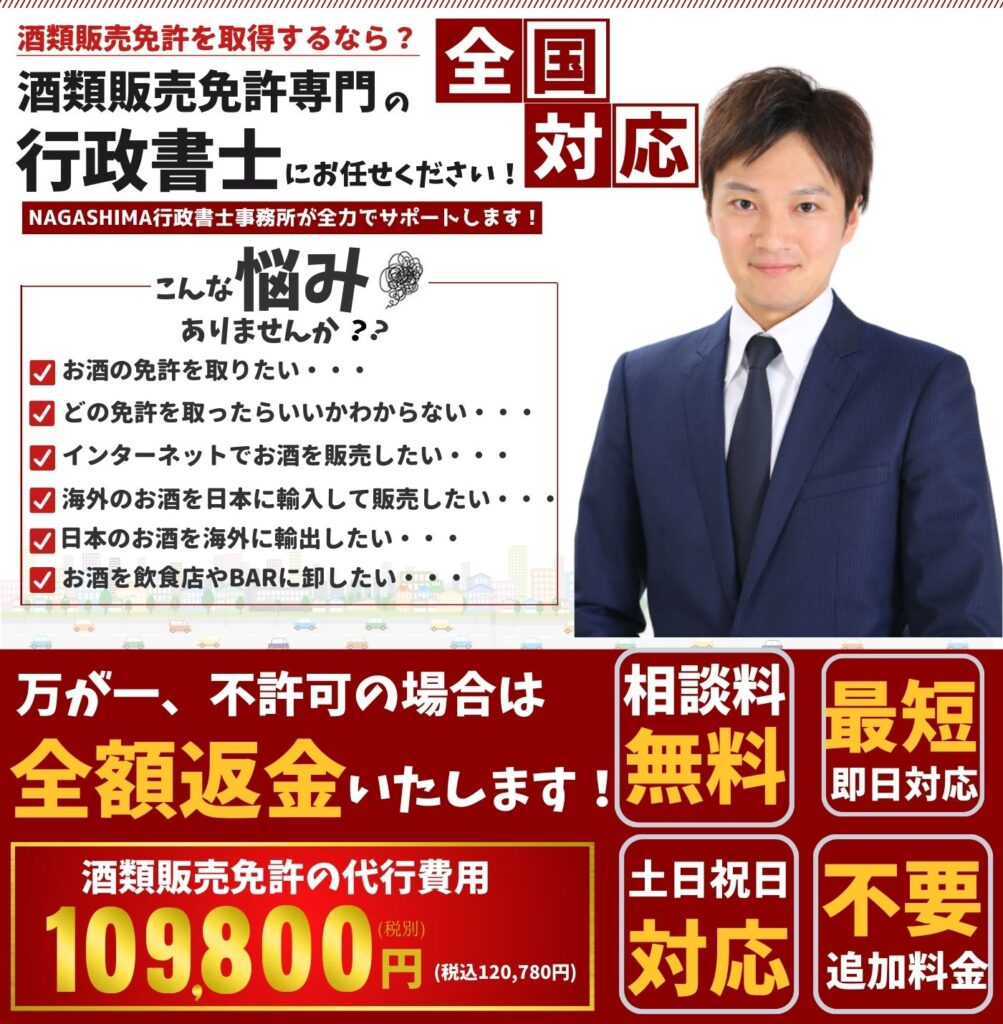

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- コンビニでお酒を販売するには一般酒類小売業免許が必要
- コンビニでお酒を販売するには店舗ごとで免許が必要
- 免許の審査に2か月かかるので取得準備は3~4カ月前から
- コンビニでの酒類販売免許の取得が不安なら専門家に相談

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所