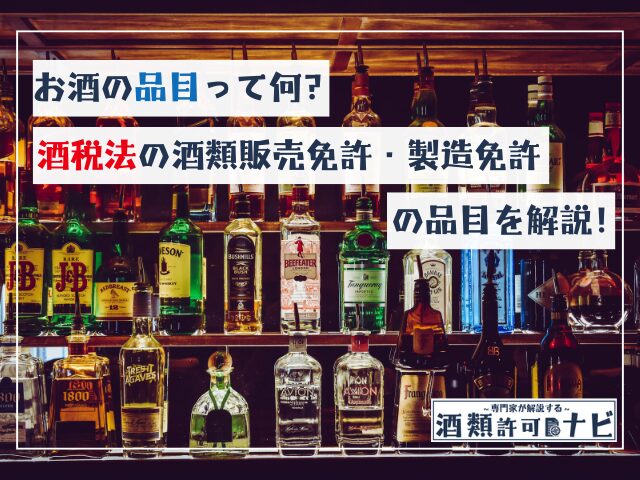
お酒にはどんな種類があるの?

お酒には色々な種類があるのですが、酒税法ではそれぞれを製造法や原料、アルコール度数などによって4種類17品目に分類しています。
この記事では、お酒の種類や品目にはどのようなものがあるのかや、品目を判断する上での注意点について解説します。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
この記事を書いた人
お酒の品目とは酒税法における分類のこと

お酒と一言でいっても、いろいろな種類のお酒がありますが、酒税法第2条第2項では、すべてのお酒をまず大きく4種類に分類し、さらに細かく合計17の品目に分けて整理しています。
具体的にはまず、大きな分類としてのお酒の製造方法によって以下の4種類に分けられます。
- 発泡性酒類(例:ビール、発泡酒など)
- 醸造酒類(例:清酒、果実酒、ワインなど)
- 蒸留酒類(例:焼酎、ウイスキー、ブランデーなど)
- 混成酒類(例:リキュール、みりんなど)
そして、それぞれのお酒は、さらに細かく区分されて「品目」と呼ばれます。
「品目」とは、原料やアルコール度数、添加物の有無、製造方法の違いによって決められる分類のことです。
たとえば、発泡性酒類には「ビール」と「発泡酒」の2品目があります。
同じ麦を原料にしていても、麦芽の使用割合や副原料の違いによって、「ビール」として扱われる場合もあれば「発泡酒」として扱われる場合もあるというイメージです。
以下では、それぞれの分類ごとの品目と特徴、具体例を解説していきます。
①発泡性酒類|ビール、発泡酒など2品目
| 発泡性酒類の品目 | 説明・特徴 | 具体例 |
|---|---|---|
| ビール | 麦芽・ホップ・水を原料に造るお酒。アルコール20度未満。麦芽比率が50%以上など、細かな条件があります。 | ビール |
| 発泡酒 | 麦芽や麦を使い、麦芽比率が50%以下のビールに似た味わいを持つ炭酸入りのお酒。アルコール20度未満。 | 発泡酒、地ビール、クラフトビール |
②醸造酒類|清酒、果実酒など3品目
| 醸造酒類の品目 | 定義の説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 清酒 | 米と米こうじ、水を原料に発酵させてこしたお酒。アルコール度数22度未満。酒かすなどを加えて造ったものも含まれます。 | 日本酒 |
| 果実酒 | ワインなど、果実を発酵させて造るお酒。アルコール20度未満。砂糖を加えて造った場合は15度未満。 | ワイン、シードル、梅酒、杏露酒 |
| その他の醸造酒 | 穀類や糖類を発酵させたもので、ビールや日本酒などに当てはまらないタイプ。アルコール20度未満で少し甘みがあります。 | 黄酒、紹興酒、蜂蜜酒、どぶろく |
③蒸留酒類|焼酎、ウイスキーなど6品目
| 蒸留酒類の品目 | 定義の説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 連続式蒸留焼酎 | 連続式の蒸留機で造る、すっきりした味わい。アルコール36度未満。 | ホワイトリカー |
| 単式蒸留焼酎 | 昔ながらの単式蒸留機で造る、原料の風味が強く残るタイプ。アルコール45度以下。 | 芋焼酎、麦焼酎、米焼酎 |
| ウイスキー | 発芽させた穀物を原料に発酵・蒸留したもの。樽で熟成させることで独特の香りが出ます。 | スコッチ、アイリッシュ、バーボン、モルト |
| ブランデー | 果実(主にブドウ)を発酵・蒸留したもの。樽で熟成させる点はウイスキーと似ています。 | コニャック、アルマニャック、カルヴァドス、グラッパ |
| 原料用アルコール | アルコール度数45度を超える、高濃度の蒸留酒。主に他のお酒の原料に使われます。 | 醸造用アルコール |
| スピリッツ | 蒸留酒の総称で、ジン・ウォッカ・ラムなど。アルコール度数は高めですが、エキス分はほとんど含まれません。 | ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ |
④混成酒類|リキュール、みりんなど6品目
| 混成酒類の品目 | 定義の説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 合成清酒 | アルコールや焼酎にブドウ糖などを混ぜて、日本酒に似せて造ったお酒。アルコール16度未満で、一定の甘みがあります。 | 日本酒風のリキュール |
| みりん | 米と米こうじに焼酎やアルコールを加えて造る調味料用のお酒。アルコール15度未満。 | 酒類調味料 |
| 甘味果実酒 | 果実酒に砂糖やブランデーを加えて甘みを強くしたもの。 | シェリー、ポート、マディラ、マルサラ、ヴェルモット |
| リキュール | 蒸留酒に砂糖や果実、ハーブなどを加えた甘みのあるお酒。カクテルに使われることが多いです。 | カシス、カルーア、ヨーグリート、電気ブラン |
| 粉末酒 | 水に溶かすとアルコール飲料になる粉末状のお酒。 | ー |
| 雑酒 | 上記どの品目にも当てはまらないお酒。新しいタイプのお酒や、変わった製法のものがここに分類されます。 | 濁酒、灰持酒 |
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
酒類の品目判断が難しい3つの理由

お酒を分類する「品目」は、酒税法で細かくルールが決められています。
ところが、この品目の判断はとても難しく、その理由は大きく分けて以下の3つです。
①原料や製法のわずかな違いで分類が変わる
酒税法における品目の分類は、使用する原料や製造方法の違いによって、全く異なる品目に分類されてしまうことがあります。
たとえば、この記事の冒頭でも少し触れた「ビール」と「発泡酒」です。
これらのお酒は見た目や味わいが似ていても、酒税法上は別の品目に分類されます。
| 品目 | ビール | 発泡酒 |
|---|---|---|
| 麦芽使用比率 | 50%以上 | 50%未満 |
| 使用する副原料 | 法律で定められている原料 | 法律で定められている以外の原料 |
| 副原料の使用比率 | 5%以内なら | 5%以上なら |
このように、消費者が「ビール系の飲み物」として一括りにしている商品も、法律上は原料や製造方法の違いから違う品目と分類されるため判断が難しいです。
②法改正で基準が変更されるケースがある
酒税法は、社会情勢の変化やお酒の多様化に対応するため、これまでに度々改正がされてきました。
そして、この法改正によって品目の定義や税率の基準などが変更されることがあります。
たとえば、2018年4月1日の酒税法改正によりビールの定義が変更されました。
具体的には、主に以下の2点が変更されました。
| 改正前の条件 | 改正後の条件 | |
|---|---|---|
| 麦芽使用比率 | 麦芽使用比率が約67%以上 | 麦芽使用比率が50%以上 |
| 使用可能な副原料 | 麦、米、とうもろこしなどに限定 | 果実やコリアンダーのような香辛料、ハーブ、野菜、そば、みそ、かつお節といった、これまで認められていなかった多様な副原料の使用が可能に。 |
つまり、これまではビールと分類されていなかった飲料についても、法律改正後にビールへと分類が変更されるケースがあるというわけです。
そのため、法律改正などの情報を細かくチェックしていないと、正しい品目の判断ができません。
③海外の酒類は日本の法律で解釈が必要
海外からお酒を輸入して販売する場合、現地の名称や分類がそのまま日本でも同じ品目に分類されるとは限りません。
なぜなら、お酒に関する法律や定義は、国によって大きく異なるからです。
例えば、海外ではビールとして販売しているお酒が日本では発泡酒として分類されたり、ワインとして販売されているお酒が甘味果実酒に分類されるケースも良くあります。
そのため、海外のお酒を取扱う場合には、お酒の成分や製造方法を確認し、日本の法律に照らし合わせて判断する必要があります。
酒類の品目を正しく判断すべき3つのポイント

これから酒類製造免許や販売免許を取得しようと考えた時に、酒税法で定められている「品目」を正しく理解することはとても大切です。
なぜなら、取り扱おうとするお酒の品目がどれに該当するかで以下の3つの点が異なるからです。
①製造・販売する品目によって取得する免許が異なる
お酒を事業として扱う場合には、必ずその品目に応じた免許を取得しなければなりません。
つまり、同じ「お酒」でも、ビールや日本酒、ウイスキーなど品目が違えば、必要になる免許の種類も変わってきます。
酒類免許は大きく分けると「酒類製造免許」と「酒類卸売業免許」、「酒類小売業免許」の3種類があります。
- 酒類製造免許・・・お酒を作るための免許
- 酒類卸売業免許・・・お酒を酒類販売業者に卸す免許
- 酒類小売業免許・・・お酒を一般消費者に売るための免許
たとえば酒類製造免許の場合、ビールを造るなら「ビール製造免許」、清酒を造るなら「清酒製造免許」といったように、品目ごとに免許を取る必要があります。
酒類卸売業免許についても同様で、扱うお酒の種類によって「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「自己商標卸売業免許」など、取得すべき免許が分かれています。
一方、酒類小売業免許は少し仕組みが異なり、扱う品目で分かれるのではなく、「店舗販売か通信販売か」といった販売方法によって必要な免許が決まります。

売りたいお酒の品目が分からない…
どの種類の免許を取得すればいいのか分からない…

そんな方は、酒類許可ナビ代行にご相談ください。
酒類許可ナビ代行では、あなたのビジネスに合った必要な免許を専門の行政書士が無料で診断致します。
\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/
▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。
②酒類の品目によって税率が大きく異なる
酒類の品目を正しく判断しなければならない2つ目の理由は、品目によって課される酒税の税率が大きく異なり、それが商品の価格や利益に直接的な影響を与えるからです。
特に、酒税を国に納める義務を負うのは、原則としてお酒を製造した酒類製造業者です。
そのため、製造業者にとって品目ごとの税率の違いはとても重要なのです。
例えば、2017年度の税制改正に基づき、これまで複雑だったビール、発泡酒、第3のビール(新ジャンル)の税率は、2026年10月にかけて段階的に以下のように一本化されることになりました(財務省|酒税に関する資料)。
| 品目 | 2023年9月まで | 2023年10月~ | 2026年10月~ |
|---|---|---|---|
| ビール | 70円 | 63.35円 | 54.25円 |
| 発泡酒 | 46.99円 | 46.99円 | 54.25円 |
| 第3のビール | 37.8円 | 46.99円 | 54.25円 |
この表から分かるように、2023年10月の改正でビールは減税された一方、第3のビールは増税となり、両者の価格差が縮まりました。
そして最終的には2026年10月に、これらのビール系飲料の税率は350mlあたり54.25円に統一される予定です。
このように、品目の違いによって税額が異なったり、税制改正により事業に大きな影響が出る可能性があります。
③輸入する酒類のラベルの品目表記が異なる
酒類の品目を正しく判断する必要がある3つ目の理由は、特に酒類の輸入卸売業者・輸入小売業者にとって重要です。
なぜなら、海外から輸入したお酒を日本国内で販売する場合には、日本の酒税法に基づいた正しい品目をラベルに表示する義務があるからです。
具体的には、海外から輸入したお酒には以下の内容を記載する必要があります。
注意すべき点は、海外での分類と日本で分類が必ずしも一致しない点です。
もし誤った品目を表示すると、表示義務違反として行政処分を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
酒類の品目に関するよくある質問

酒類の「種類」と「品目」はどう違うのですか?
一般的に種類は製造方法によって大きく分けられる4つの分類のことを言います。一方、品目は4種類をさらに原料やアルコール度数、添加物の有無、製造方法で分けた分類のことを言います。
同じビール系飲料でも、なぜ「ビール」と「発泡酒」に分かれるのですか?
麦芽使用比率や副原料の種類・割合によって法律上の区分が異なるからです。
免許を取れば、どの品目でも自由に製造できますか?
製造免許は品目ごとに分かれており、ビール免許でワインを作ることができません。
酒類の品目は今後変わる可能性がありますか?
酒税法改正により基準が変更され、品目が変わる可能性はあります。
品目が分からない場合にはどこに確認すればいいですか?
税務署や国税局に確認することが可能です。また、免許の申請等も検討している場合には行政書士などの専門家に相談することも可能です。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
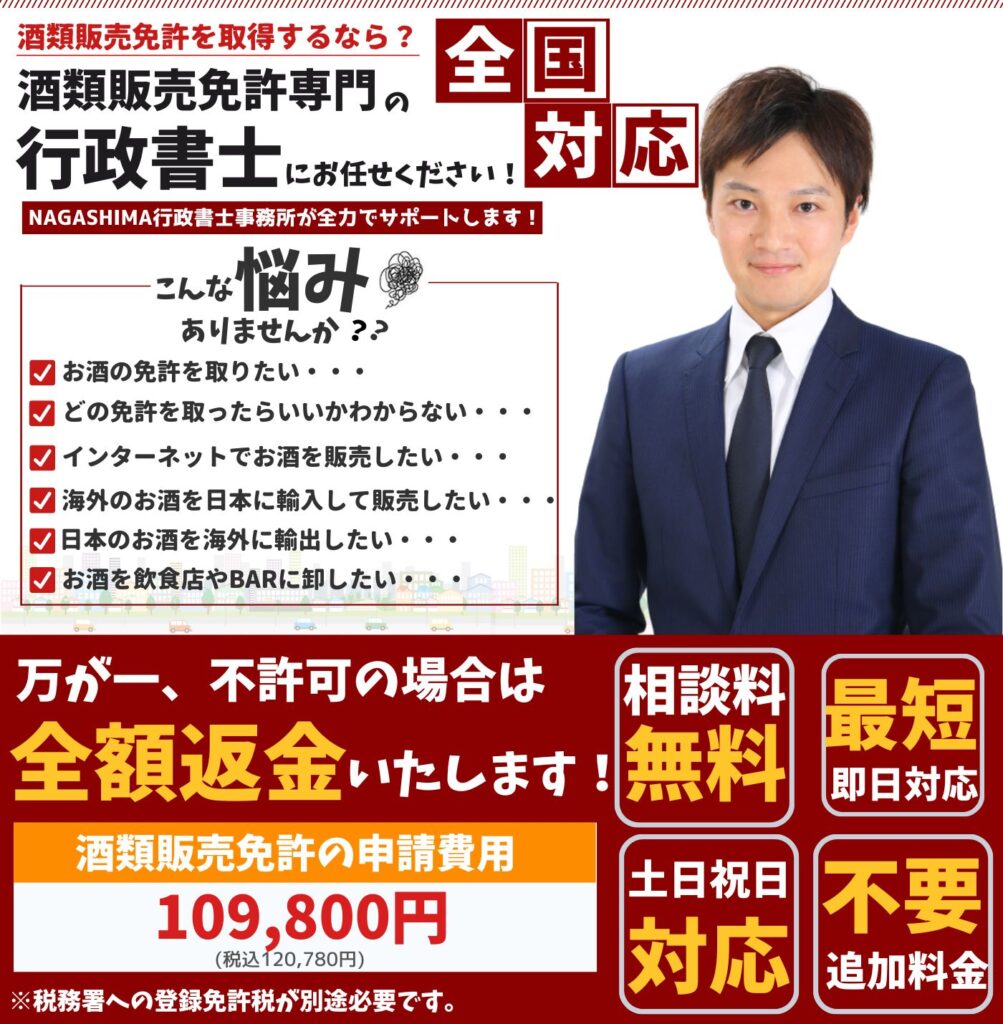

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- お酒の品目は4種類17品目に分けられる
- お酒の4種類は製造方法で分類される
- お酒の17品目についてはアルコール度数や原料などで分類される
- 法改正により品目が変更されるケースもある
- 酒類製造・販売免許は品目に合わせて取得が必要

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所