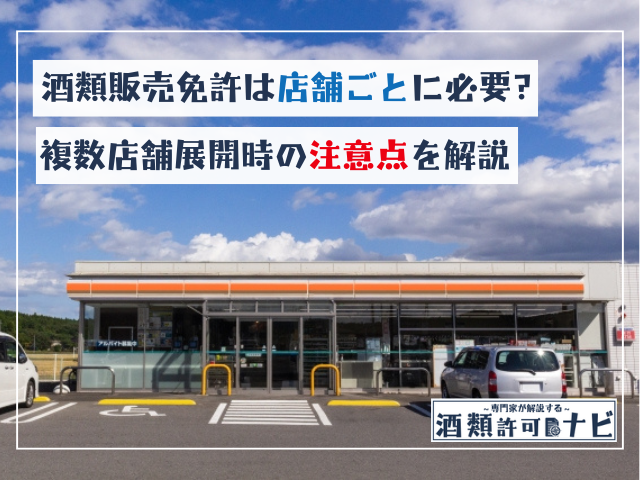

酒類販売免許は店舗ごとに必要?
店舗を増やす場合の注意点はある?

これから店舗を増やすことを検討している方の中には、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
結論を先に行っておくと、酒類販売免許は店舗ごとに取得する必要があります。
そこで、この記事ではこれから複数の店舗でお酒を販売したい方向けに、免許の必要性や注意点について専門家が解説します。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
この記事を書いた人
酒類販売免許は「店舗ごと」に必要?

結論からいうと、酒類販売免許は「店舗(販売場)ごと」に取得する必要があります。
たとえ同じ法人や個人がお酒を販売する場合でも、販売する場所が異なれば、それぞれの店舗ごとに免許を取得する必要があります。
これは、酒税法第9条により酒類販売免許は販売場ごとに免許を受けなければならないと規定されているからです。
たとえば、既に東京で酒類販売免許を取得した店舗があり、事業が好調で名古屋にもう1店舗を展開する場合、それぞれの店舗が「別のお店」と見なされ、名古屋で新たに酒類販売免許を取得しなければならないということになります。
もし、名古屋の店舗で酒類販売免許を取得せずにお酒を販売した場合、仮に東京の店舗で酒類販売免許を持っていたとしても無免許販売となる点は注意が必要です。
しかも、無免許でお酒を販売した場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。(酒税法第56条)
また、既に取得している免許も取り消されてしまうかのせいもあるので、別の店舗でお酒を販売する場合には、必ずそのお店で免許を取得するようにしましょう。
なぜ店舗ごとに免許が必要なのか?
酒類販売免許を取得した方の中には、「法人や個人で許可を取れば、その許可で他の店舗でも使えるのでは?」と思う方もいるかもしれません。
たしかに、他の許可では「人」や「会社」に対して与えられるケースもありますが、酒類販売免許は『誰が・どこで』お酒を売るか、という「人×場所」の組み合わせに対して許可が与えられます。
つまり、「誰がどこでお酒を売るのか?」が重視される為、販売する場所が異なったり、販売する人や法人が異なれば、お酒を販売することはできません。
その結果、それぞれの店舗ごとでお酒の免許を取得する必要があるというわけです。
酒類販売免許を店舗ごとに取得する際の注意点

酒類販売免許を1店舗目に新規で取得する場合と異なり、複数出店する場合に独自の注意点があります。
具体的には以下の点で注意が必要です。
2店舗目以降も場所的要件を満たす必要がある
酒類を販売する店舗を、新たに2店舗目、3店舗目と展開する場合、それぞれの場所で酒類販売免許を取得しなければなりません。
つまり、1店舗目で酒類販売免許を取得した時と同様に、販売場の要件を満たす必要があります。
たとえば、土地や建物の所有者から承諾書を貰えるかや、土地の地目が宅地になっていかなど、販売場としての条件が一つひとつチェックされます。
そのため、「1店舗目が通ったから、同じような物件なら大丈夫だろう」と安易に考えてしまうと、場所的要件を満たせずに不許可となる可能性もあるため注意が必要です。
酒類販売場の要件について詳しく確認したい方は「酒類販売免許の販売場とは?営業所・事務所の要件をわかりやすく解説」の記事で分かりやすく解説しているので確認してみてください。
免許の種類は販売店ごと
酒類販売免許は店舗ごとに免許を取得するため、それぞれの販売場ごと免許の種類を変えることも可能です。
たとえば、1店舗目では店頭販売用に「一般酒類小売業免許」を取得し、2店舗目ではネット販売専用として「輸出卸売業免許」を取得する、といった使い分けができます。
このように、販売する場所ごとに販売方法や営業形態に応じた免許を取得することができるため、店舗ごとに最適な免許の種類を選びましょう。
同じ建物内で複数の販売場を設置
酒類販売免許は「販売場ごと」に取得が必要なため、たとえ同じ建物内であっても、販売エリアが明確に分かれていれば、それぞれの場所で個別に免許が必要になることがあります。
たとえば、ショッピングモールや商業施設のような物件で、1つの法人が異なる区画に複数の販売拠点を構える場合、それぞれの区画が独立した販売場と判断されると、免許もそれぞれに取得しなければなりません。
逆に、契約内容や構造上、ひとつの販売場として認められる場合は、1つの免許で販売できるケースもあります。
このように、「住所が同じだから1免許で大丈夫」とは限らず、販売場としての区画やどれぐらい離れているか、物件によって判断が分かれるため、事前に専門家や税務署へ相談することをおすすめします。
帳簿の管理は各店舗ごとで行う
酒類販売業者には、お酒の取引内容などを記帳する義務があります。
そして、この帳簿は販売場ごとに備えつける必要があるのです。
例えば、東京に1店舗、大阪に1店舗のお店を出店している場合、東京と大阪のお店でそれぞれ台帳を作成しなければなりません。
つまり、東京と大阪の取引をまとめて東京の店舗で管理するということはできません。
店舗ごとの免許取得で不安な方は専門家に相談

酒類販売免許は店舗ごとに申請が必要で、場所的要件や免許の種類、帳簿の管理など、確認すべきポイントが多くあります。
とくに2店舗目以降になると、「この物件で本当に通るのか?」「どの種類の免許を選べばいいのか?」といった不安を感じる方も少なくありません。
そういったときは、行政書士などの専門家に早めに相談するのがおすすめです。
物件選びの段階から相談できれば、要件を満たすかどうかを事前にチェックしてもらえますし、申請書類の準備や税務署とのやりとりもスムーズに進みます。
複数店舗を展開するほど手続きは煩雑になりやすいため、「失敗したくない」「無駄な時間をかけたくない」と考えている方は、専門家の力を借りて確実に進めることが大切です。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
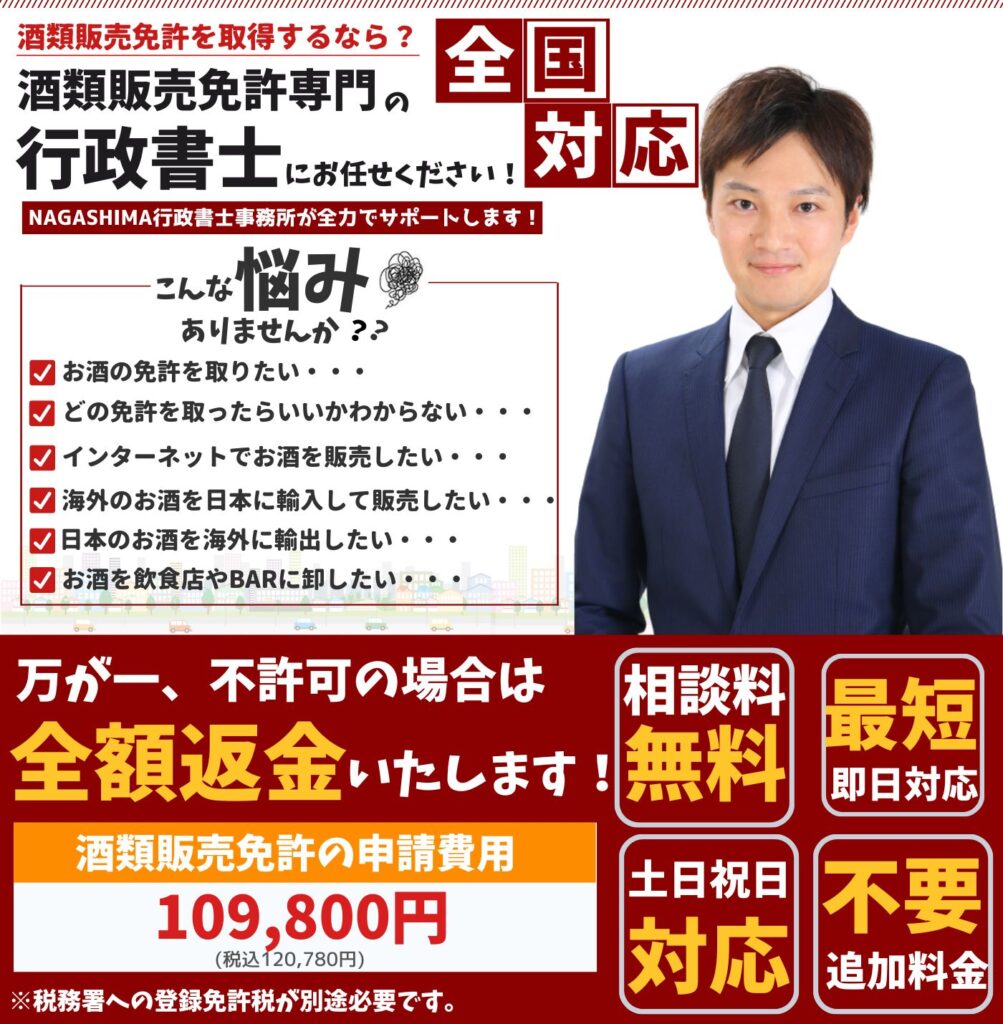

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- 酒類販売免許は販売場ごとに取得が必要
- 2店舗目以降も場所的要件を満たす必要がある
- 帳簿の管理も販売場ごとに管理する
- 複数店舗で出店する場合は行政書士に相談

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所