

何をすると酒類販売業免許を取り消されるの?
免許を取り消されない為の対象法ってある?

このような不安や疑問を抱えている方も多いです。
そこで、この記事では、どのような場合に酒類販売業免許が取り消されるのかや、取り消されないための対策について分かりやすく解説します。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
この記事を書いた人
酒類販売免許の4つの取消事由

酒類販売業免許には更新期限がないので、免許を取得すれば基本的には一生使い続けられます。
ただし、ルールを守らずに酒類販売を続けた場合には、免許を取り消されてしまうことがあります。
具体的には、酒類販売業免許の取消事由として以下の4つが定められています(酒税法第14条)。
①嘘や不正で酒類販売免許を取得したことが発覚した場合
酒類販売免許の申請時に、事実と異なる内容を記載した書類を提出したり、不利になる情報を意図的に隠したりして免許を取得した場合、その後に発覚すると免許は取り消されます。
具体的な例としては、次のようなケースが考えられます。
- 本当は赤字なのに、黒字に見せかけた決算書を提出した
- 店舗の使用権限がないのに、契約があるかのような書類を作って提出した
- 実際には別の場所で営業する予定なのに、違う場所を販売場として申請した
- 自分は酒類販売を行わず、別の人に免許を貸すために取得した
こうした行為は「たまたま」や「軽い間違い」ではなく、酒類販売免許の根幹を揺るがす重大な不正と見なされます。
②免許取得後に酒類販売免許の欠格事由に該当した場合
免許を取得した時点では問題がなくても、その後に「欠格要件」に当てはまってしまうと、免許は取り消される可能性があります。
酒類販売免許の欠格事由とは、該当すると酒類販売免許を取得できない要件のことで、具体的には、以下に該当する場合に免許を取り消される可能性があります。
ちなみに、酒類販売業免許を新規で取得する際には、「3期連続赤字ではない」「債務超過ではない」といった要件を満たす必要があります。
しかし、酒類販売免許取得後に、3期連続で赤字になったり、債務超過になったりしたとしても、免許の取消事由にはならないので安心してください。
③正当な理由なく2年以上酒類販売業をしていない場合
お酒の販売免許を取得しても、2年以上まったく販売を行っていない場合は「事業を続ける意思がない」と判断され、免許が取り消される可能性があります。
これは免許を取得したまま放置したり、不正利用されることを防ぐためです。
具体的なケースとしては、次のようなものがあります。
- 免許を取ったものの、店舗の開店準備を進めず2年以上経過してしまった
- 税務署に理由を伝えないまま、長期間お店を閉めている
- 販売数量報告書を2年以上提出していない
販売数量報告書とは、年に1度、お酒の販売数量や在庫数量等を税務署に報告する書類のことで、実際に販売実績がなくても毎年提出しなければなりません。
この書類が提出されていないと、税務署は「休業している」と判断する可能性があり、その結果、2年以上休業していると判断されて免許を取り消されてしまう恐れがあります。
一方で、経営者の長期療養や大規模な改装工事など、やむを得ない「正当な理由」がある場合は対象外となります。
④酒類業組合法の命令に違反した場合
酒類業組合法とは、酒税をきちんと確保し、業界全体の公正な取引を守るために定められた法律です。
この法律に基づいて税務署長から命令が出され、それに従わなかった場合は免許が取り消される可能性があります。
命令には主に以下の2つの種類があります。
そして、これらの命令が出ているにも関わらず、無視して営業を続けた場合には、免許取り消しの対象となります。
酒類販売免許の取消を防ぐための対処法
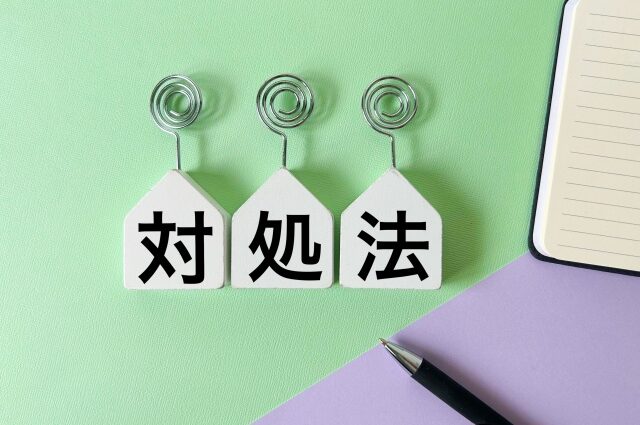
ここまで見てきたように、酒類販売免許は一度取得しても「不正な申請」「欠格要件に該当」「長期の休業」「命令違反」といった事由に当てはまれば取り消されてしまう可能性があります。
では、こうしたリスクを避けるにはどうすればよいのでしょうか。
大切なのは、免許取消につながる行為を未然に防ぎ、もし問題が発生しても迅速に対処することです。
具体的には次のような対処法が挙げられます。
新規取得時に不正な申請はしない
酒類販売免許の取消を防ぐための最も基本的で、そして最も重要なことは、これから免許を申請する段階で、絶対に嘘をつかないことです。
当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、中には虚偽の内容で申請して許可を取得しようとする方もいます。
というのも、酒類販売業免許には要件があるので、その要件を満たせずに免許取得を断念する方も少なくありません。
そして、中には「どうしても免許を取りたい」という思いから、虚偽の内容で申請してしまう人もいるというわけです。
さらには、軽い気持ちで悪気もなく事実と頃なる内容で申請したけど、法律上はかなり重大な違反に該当するケースも考えられます。
そのため、絶対に虚偽の内容で申請しないようにしてください。
酒類販売免許の取消事由を解消する
万が一、ご自身の事業が酒類販売免許の取消事由に当てはまってしまった場合でも、当てはまったからといって自動的に免許が取り消されるわけではありません。
免許の取消は、税務署による行政処分なので、多くの場合、問題が発覚してから処分が下されるまでには、事実確認や指導といった段階があります。
この段階で、問題を解決するために迅速かつ誠実に対応すれば、免許の取消を免れることが可能です。
実際に取るべき対応の例を挙げると、次のとおりです。
取消事由に当てはまってしまった場合には、絶対に隠したり放置したりしないようにしましょう。
過度な安売りを避けて適正な価格で販売する
酒類販売免許を維持するためには、販売するお酒の価格設定にも注意が必要です。
お酒を安く販売すること自体は問題ありませんが、周囲の店舗が経営できなくなるほどの極端な安売りを続けると、取引の公平さを壊す行為として「酒類業組合法の命令」が出される可能性があります。
対処法としては、まず採算を度外視した価格設定を避け、利益がきちんと出る範囲で販売するようにしましょう。
通常のセールやキャンペーンであれば問題ありませんが、長期間にわたって原価割れの価格で売り続けるような行為はリスクがあります。
また、自社だけでなく地域全体のバランスを意識した価格設定を行うことも、免許を守るための有効な方法だといえます。
酒類販売免許専門の行政書士に相談する
酒類販売免許は一度取得すれば終わりではなく、思わぬことで取消事由に当てはまってしまう可能性があります。
そのようなときに頼りになるのが、酒類販売免許を専門に扱う行政書士です。
行政書士は、法律の知識を持っているだけでなく、過去の申請事例や税務署が実際にどのように対応するかもよく理解しています。
そのため「このケースは取消に当たるのか」「改善すれば免許を維持できるのか」といった判断や対応方法を具体的にアドバイスが可能です。
「自分で何とかなるだろう」と放置してしまうと、問題が大きくなって免許取消につながるリスクもあるので、少しでも不安を感じたら、早めに行政書士に相談することをおすすめします。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
もし免許取消処分を受けたら?|不服がある場合の唯一の対処法

万が一、税務署から酒類販売免許の取消処分を受け、その内容に納得がいかない場合でも、すぐに諦める必要はありません。
法律では、事業者が不服を申し立てられる正式な手続きが用意されています(国税通則法第80条)。
具体的には、次の2つの方法があります。
国税不服審判所への「審査請求」
免許取消処分に納得できない場合は、「審査請求」をすることができます。
これは処分の見直しを求めるための正式な手続きで、判断は税務署ではなく国税不服審判所が行います。
- 申立て先:国税不服審判所
- 申立て期限:処分を知った日の翌日から3か月以内
- 特徴:裁判に比べて手続きが簡単で、比較的早く結論が出やすい
なお、期限を過ぎると申し立てはできません。
取消処分の通知を受けたらすぐに準備を進め、必要であれば行政書士や弁護士に相談すると安心です。
裁判所への「処分の取消しの訴え」
国税不服審判所の判断にも納得できない場合は、裁判所に「処分の取消しの訴え」をすることができます。
これは、裁判を通じて「取消処分が正しかったのか」を第三者である裁判官に判断してもらう手続きです。
- 申立て先:裁判所
- 申立て期限:審査請求の結果があったことを知った日から6カ月以内
- 特徴:比較的時間はかかるが、事実や法律の解釈が正しかったかを裁判所が判断
なお、期限を経過すると裁判を提起することができません。
また、酒税法の処分については、必ず先に「審査請求」をして裁決を受けてからでないと裁判できない点は注意が必要です(国税通則法第115条)。
免許取消だけではない|酒税法違反に科される厳しい罰則

酒税法に違反すると、免許の取消だけでなく、拘禁刑や罰金といった厳しい罰則を受ける可能性があります。
そのため、酒類販売免許の取消事由だけではなく、以下の点にも注意が必要です。
こうした罰則は「知らなかった」では済まされず、発覚した時点で事業の継続に大きな影響を与えます。
特に、酒類販売免許の条件は細かく複雑で、ちょっとした手続き漏れや記録の不備が思わぬ違反につながることもあります。
そのため、酒売販売の法律に不安がある場合は、酒類販売免許に詳しい行政書士へ相談しながら運営していくのがおすすめです。
\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/
▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。
酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行
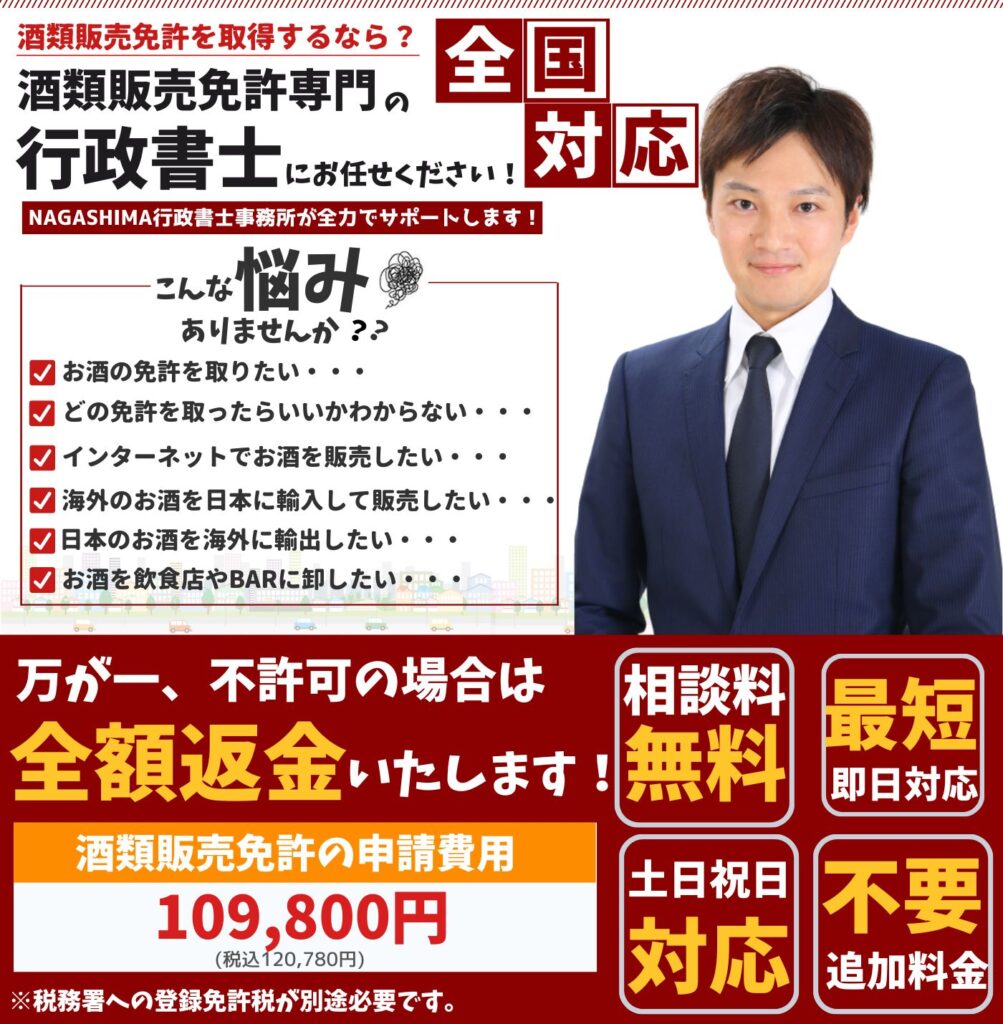

できるだけ早く免許を取得したい…
不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。
\無料診断・無料相談はこちら/
※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)
\1分でかんたん入力/
※初回相談無料・全国対応・土日OK!
まとめ
この記事のまとめ
- 酒類販売免許の取消事由は4つ
- 嘘や不正での酒類販売免許の取得が発覚したら取消される
- 酒類販売免許の欠格事由に該当する場合に取消される
- 酒類販売業を2年以上休業している場合に取消される
- 酒類業組合法の命令に違反した場合に取消される
- 取消処分に不服がある場合には審査請求・裁判を

長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所